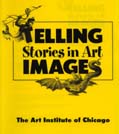シカゴ美術館における教育プログラムの紹介
イリノイ大学シャンぺ−ン校 中村和世
民主主義の思想を社会の基盤としているアメリカでは、美術館開設当時からその役割の1つは市民教育にあるという考え方を基に美術館運営がなされてきた。美術館は、実生活と直接関わりのない物品を安置している場所であり社会の上層的階級の人々のみが集う場所であるというよりも、すべての人々が個人の生活や社会の質を向上させるために教養を高める場所であるとして捉えられてきた。アメリカの3大美術館に含まれるシカゴ美術館は、ニューヨーク近代美術館やメトロポリタン美術館と並んで早くから地域の人々や学校と関わりながら教育活動を展開している。美術館教育と一言でいっても、美術館ツアーから市民を対象とした生涯学習プログラムまで幅広いが、この紹介では、学校教育と直接関連のある教育プログラムについて焦点をあてる。紹介のために、シカゴ美術館教育課教材開発部(Teacher Resource Center)の主任であるジーン・プール女史がシカゴ美術館教育についてインタビューに応じてくれたり館内にあるクラフト教育センター(Kraft Education Center)を案内してくれた<1>。本稿では、シカゴ美術館の教育史について概説した後、次の3項目を中心にしてシカゴ美術館の教育プログラムを紹介する。1つ目は、学校と連携して行われている具体的な教育実践についてである。2つ目は、学校教師のために開かれている美術館でのワークショップや講座についてである。3つ目は、シカゴ美術館教育課で開発されている鑑賞学習教材の内容についてである。日本においても特に鑑賞教育の充実のために学校と美術館との連携が求められているが、シカゴ美術館の教育実践例がその参考となればと考えた。
1. シカゴ美術館教育の概略
シカゴ美術館での初期的な教育活動は、1895年頃にフレンチ館長(W.M.R.French)が開設したギャラりーにおける講演プログラムに始まる<2>。このプログラムは、美術の業界に直接従事しない一般人でも所蔵作品について理解を深め公衆の生活に美術を普及することを目指して開設された。講演プログラムは一般市民のための美術鑑賞教育の一例であるが、特に学校教育と関わりをもった教育実践は1950年代頃から始められている。現在の美術館教育からみれば簡素なものであるが、学校から見学にきた子供達の団体に対する引率者つきの美術館ツアーはその当時から行われている。また、ピクチャー・レディー(Picture Lady)と呼ばれる教育活動が1960年代頃から始められている。ピクチャー・レディーとは、父兄や婦人団体のメンバーが美術館所蔵作品の複製を美術館から借りて、主に小学校に出掛けて行き放課後を利用して作品について説明したり子供達と話し合ったりする活動のことである。学校により異なるが、ピクチャー・レディーに参加しているボランティアは月に2、3回学校を訪問する。この教育活動は美術館の所蔵作品についてよく知ってもらうことで地域住民と美術館とのつながりを深めることを目的としている。このような教育活動に加えて、美術館教育施設に関しては、1961年に館内に現在のクラフト教育センターが設置され美術館教育プログラムの充実と制度化が本格的に進められた。センターには、学校から美術館見学にきた子供達が昼食を取ったり、週末や夏休みに行われるワークショップで制作活動が行える2室が備えられている。また、子供用図書館や美術に関する映画やパフォーマンスを視聴できる上映室が設けられている。このように館内に子供用の学習スペースを提供することで、1960年代から現在にかけて美術館の教育的役割がさらに拡張されている。
今日のシカゴ美術館では、総勢約1100人の館職員のうち、42人が美術館教育に従事している。美術館教育課は広報部、教育プログラム企画部、展示企画部など細分化されており、そのうち3人の職人から運営されている教材開発部が中心となって学校と美術館の教育における連携を図っている。教材開発部の主な役割は、美術館で行われる教師用ワークショップの斡旋、学校からの美術館見学の手配、鑑賞教材やワークシートの開発などである。館内地下のクラフト教育センターにある教育開発部は、季節によって異なるが週に4日間教師のために開室されており、カリキュラム開発や授業創りに必要な教材を無料で貸し出している。また、教材開発部を訪問・利用した教師に対して、1年間有効である美術館入館フリーパスを提供し教材開発の上での美術館利用を施している。このほか、教材開発部では児童・生徒グループの美術館ツアーを充実させるために担当教師に対して事前学習の相談にのったり、常設展のみでなく特別展の資料や教材を提供している。美術館へは、シカゴ美術館のあるイリノイ州のみでなく隣接州であるウィスコンシン州やインディアナ州の学校からの来館があるが、幼稚園から高等学校を含めてツアー参加者は昨年では約16万人であったそうである。
2. 学校教育との連携を図った教育プログラム
シカゴ美術館では、1960年代から学校と関わりながら教育活動が展開されてきたが、過去10年間にわたって学校との連携を強めるために特別企画展を含む教育プログラムが開発されている。このプログラムは、1987年から始められている美術共同プログラム(Art Partners Program)で、次のような4つの内容をその目的としている。それらは、「児童・生徒の視覚的解読能力を高めること」、「イリノイ州とシカゴ地区の教育方針に基づいた学習を継続して提供すること」、「児童・生徒や教師のシカゴ美術館に対する認識を高めること」、「シカゴ美術館の館外教育活動(Outreach Educational Program)をシカゴ公立学校において充実させること」である。そして、3つの活動を基軸にしてプログラムを構成している。1つ目は、シカゴ美術館所蔵作品について芸術家が介入した学校での授業を4回行うことである。この学習には、美術史の学習、美術用語の習得、制作活動が含められている。2つ目は、2回の美術館訪問を通して対象作品についてさらに学習を深めることである。3つ目は、美術館での学習後、学校で短い感想文を書くことなどを通して学習を振り返ることである。このように学校と美術館の両方の場所を利用した共同教育モデルは1990年代に企画された異文化教育を目的とする2つの特別企画展に適用され、その効果に関する調査と教育モデルの改善が継続して試みられている。
共同教育プログラムや美術館ツアーにおいて、鑑賞指導には美術館教育者や学校教師のみではなく、ドーセント(Docent)と呼ばれる一般市民からのボランティアが協力・参加している。ド−セントとは、鑑賞指導について美術館教育者や学芸員から特定の訓練を受けた美術館ツアー引率者であり、退職した学校教師や婦人団体のメンバーがドーセントとして活躍している。シカゴ美術館では、120人のド−セントが美術館教育の運営を援助しており、ドーセントの1人1人が年に18回の美術館ツアーを担当することになっている。
シカゴ美術館では、1日1学校90人までの児童・生徒の団体をツアーのために受け付けており、学校教師は来館以前に教材開発部に連絡を取ってドーセントや美術館教育者と話し合い、学校の授業で事前学習を行うことが勧められている。教材開発部には常設展のみでなく特別展についてもスライドを含む教材やワークシートが用意されている。ド−セントは、児童・生徒が来館する前に教師に連絡をとり学習者について予備調査をしたり、どのような事前学習をしたのかについて情報交換することになっている。ツアーでは、ド−セントが美術作品について説明するのみではなく、児童・生徒達が中心となってディスカッションがなされる。ツアーは約1時間でその間に約8つの作品についてドーセントと話し合いを進める。ツアーの内容は特別展または常設展を合わせて約21のテーマから選択できるようになっている。
3.教師用プログラム
学校教師に美術館を利用した題材やカリキュラムを作成してもらうために、シカゴ美術館では教師に対して無料の美術館研修ツアーを提供している。この研修ツアーには、美術科教師のみではなく美術の内容を他教科の学習に取り入れることを考えている小学校教師や数学教科などの教師も参加している。この研修ツアーに参加希望の教師は、自分達が教材研究を行いたい内容についてテーマを設定し10人から30人のグループを作って、教材開発部に申し込むことになっている。研修では、テーマに関する所蔵作品について学芸員、美術館教育者、またはドーセントの指導で美術館のギャラりーを活用して学習できる。このような研修ツアーは、個々の教師が学校で所蔵作品に関する題材を創造的に開発することを促すものであり、教材開発部では授業創りに役立つ資料やスライド等を参加教師に提供している。
また、年内を通して学校教師のためにワークショップや講座が開かれている。ワークショップや講座の指導者は、学芸員、芸術家、学士・修士課程のあるシカゴ美術館美術学校の教諭が担当している。講座によっては単位が取得できるようになっており、教材開発部主任のプール女史によれば、ある程度の単位を取得することで教師の昇進が早められたり年俸が上げられるそうである。ワ−クショップや講座の内容は半年ごとに改訂されており、2001年1月から6月には美術史について8コースが開講された。ワークショップや講座は、大抵1日コースであり、教師が参加できる金曜の夕方、土・日曜の週末に限られている。参加費については、スライドなどを含む教材が提供される場合は有料で、午前9時半から始まり午後3時半に終了するワークショップで約25ドルである。参加教師は、ワークショップや講座で学習したことを基にして学習指導案を作成することが勧められており、指導案は教師の任意で教材開発部に寄付されている。寄付された指導案は他の教師が参考として閲覧できるよう教材開発部に保管されている。また、いくつかの指導案はインターネットを通してシカゴ美術館によって公開されている。
その他、BASIC (Basic Art Support in the Curriculum)と呼ばれる教師用プログラムが開かれている。このプログラムは、地域の教師の制作活動や学校での美術に関する指導技能を高めることを目的とし、イリノイ州の教育委員会で規定された教育規範(Illinois Professional Teaching Standards)に基づいて内容が選択決定されている。2001年の1月から6月には美術制作や地域における美術教育プロジェクトなどに関して9つのコースが無料開講されている。これらのコースは、主に画家や彫刻家また学校の美術教師が指導者となっている。また、学校教師達が学習の場所として利用するのみでなく、他の教師達と出会い教育問題について話し合ったり共同研究について考えたりする場所となっている。
4.鑑賞教育と教材開発
シカゴ美術館では、アメリカの美術館教育で普及しつつある「視覚的思考方法(Visual
Thinking Strategies)」<3>を用いて鑑賞指導を行っている。視覚的思考方法とは、表1に示すような4つの質問内容を基軸として展開される鑑賞学習法で、創造的思考力、コミニュケーション技能、イメージを解読する能力(Visual Literacy)の育成を目指している。この方法は、マサチューセッツ大学の認知心理学者であるアビゲイル・ハウゼン(Abigail Housen)とニューヨーク近代美術館の美術館教育者であるフィリップ・イェナバイン(Philip Yenawine)によって開発され、その学習効果についてニューヨークの公立学校を利用して研究が続けられている。日本では1995年に水戸美術館で研修が行われ、アメリカでは美術館教育のみでなく教員養成を含めた教師教育にも適用されている。シカゴ美術館では、視覚的思考方法を活用して、美術館ツアーを引率するドーセントを訓練したり、学校教育で鑑賞教育に携わる教師を指導している。
また、現代の教育課題に関連した特別企画展をクラフト教育センターで開き、企画展に基づいた教材開発を行っている。例えば、1996年からは「語りかけるイメージ:美術作品にみられる物語り(Telling Images: Stories in Art)」という子供の視点に合わせた企画展を開いている。この特別展は多文化教育を念頭に置き、異文化美術において伝達される物語や共有される知識をテーマとし、次の4つの内容を企画の特徴としている。1つ目は、異なる文化圏であるヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、インドから合計6点の作品を選択していることである。2つ目は、民話、宗教、神話、歴史、自叙伝など物語りに関する作品を展示していることである。3つ目は、異なる表現方法で制作された作品を選択していることである。企画展では、絵画から3点、彫刻から2点、写真から1点が展示されていた。4つ目は、子供が参加できる異文化空間を展示作品の周囲に設けていることである。会場では、作品の周囲に小部屋のようなしきりが用いられ、小部屋には作品が存在した文化的環境の再現が試みられていた。例えば、彫刻作品であるインドの神像については、神像が安置されていた神殿の様子に従って小部屋が設計されていた。
また、このような特別企画展ごとに作品のスライドや指導案を含む教材が学芸員や美術館教育者によって開発されている。例えば、「語りかけるイメージ:美術作品にみられる物語り」の特別企画展に基づいて作成された教材冊子には、1作品ごとに約15ページ程の作品説明と学習指導案が載せられてている。作品説明の部分では、作品が制作された当時の社会的状況や文化的環境に焦点が当てられており、作品が美術としてのみでなく歴史的・文化的遺産として理解されるよう配慮がなされている。学習指導案の部分では、ディスカッションのための質問の例や、美術用語のみでなく文化用語や歴史用語の説明、制作活動指導案、作文の課題の例、他教科と関連した学習活動の例について記載されている。また、教師達が自分達のカリキュラムの目的に応じて教材をさらに開発できるように関連資料のリストが載せられている。
その他、クラフト教育センターには、幼稚園児から小学生を対象とした約10ページ程のセルフガイドの小冊子が用意されている。このセルフガイドは、2001年現在では約7種類あり、「線(Line)」「仕事と遊び」「武器とよろい兜」「神様と英雄」「家具」「美術の中の動物」「美術にある物語り」のそれぞれのテーマにそって、所蔵作品について家族や友達と学べるようになっている。小冊子には、作品の複製とともに作品が展示してある美術館ギャラりーの番号が示されており、ギャラリーを訪問して遊び感覚で冊子に書き込みながら美術について学べるようになっている。
以上のように、シカゴ美術館では美術館利用者である地域住民や学校関係者の視点にたった美術館教育を設計・開発している。その政策姿勢は次の3点にあると考える。1つ目は、美術館関係者や学校関係者のみでなく市民の参加・協力を得た美術館教育を展開していることである。2つ目は、教育者に討論や学習の場を提供するなど美術館の公的教育機関としての社会的役割を認識していることである。3つ目は、ワークシートの作成や所蔵作品について学習指導案を作成するなど教材を開発・提供する機能の充実を目指していることである。アメリカと同様に民主主義の社会体制をもつ日本においても、美術館を市民の生活により親密に結び付けて機能させることで、市民教育の一端を担う美術館教育のさらなる展開が期待されると考える。
註:
1)シカゴ美術館の紹介にあたって、ジーン・プール女史が提供してくれた資料・教材のみでなくシカゴ美術館のWeb サイト:www.artic.eduを利用した。
2)Zeller, T. (1989) The historical and philosophical foundations of art museum education in America. pp.10 - 89. In N. Berry & S. Mayer (Eds.) Museum education history, theory, and practice. Reston: NAEA.
3)視覚的思考方法のシカゴ美術館における実践については、2000年にロスアンジェルスで開催されたNAEAでシカゴ美術館教育者が発表した内容のみでなく、その実践例や関連論文を紹介しているWebサイト:www.vue.orgを参考にした。
1969年福井県生まれ。福井大学教育学部卒。同大学院(修士課程)修了。インディアナ大学大学院修士課程(美術教育専攻)を経て、2000年に同大学博士課程修了。(Ph.D.)専攻=教育課程論、副専攻=教育哲学、陶芸。博士論文では、教員を目指す大学生の鑑賞学習に関する意識について質的探究を行った。現在、イリノイ大学教育政策科教育哲学研究科で客員研究員として、民主主義(特にデューイ哲学など)と美術教育の関連について研究。鑑賞教育のほか、質的探究法を用いた調査方法に関心を持っている。