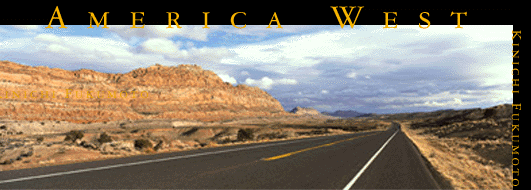
メンフイスからホットスブリングスへ
福本謹一
メンフイスを後に、ミシシッピ川を渡るとアーカンソー州である。40号線をフォードのライトだけが頼りの暗間をひたすら西へ向かって走った。ライトの中をセンターラインがゆっくりと過ぎる。90キロ程で走っているのだが、どうも日本で感じのとは違う感覚だ。センターラインの長さが違うのかもしれない。フォードのエンジン音が確かにしているのだが、なぜか夜の静寂を感じた。彼のラジカセから日本から持参していたハイファイセットの中央フリーウェイが流れる。州都のりトルロックを少し南へ迂回してホットスブリングス国立公園の近くのモーテルをとるまで、二人とも無口でそれぞれの想いにふけっていた。
翌朝、モーテルでドーナツとスチロール製の白いカップに注がれたコーヒーで朝食を済ませて、30号線を抜けたホットスブリングスに入つた。通りのあちこちに「ホットバス付きモーターイン」とか「バスハウス」と書いた看板が目に付く。バスハウスは銭湯のことである。そこではじめてホットスプリングスが名の通り、「温泉」であることに気づいた。土地のアイデンテイティーがこれほど分かり易いところはないかもしれない。土地柄という言葉があるが、その土地「柄」なり「景色」はパターンや色合いという視覚的な認識の強い言葉である。こうした土地に来ると、その視覚的要素もさることながら、風の匂いや人々の眼差しや仕草といった皮膚感覚なものに敏感になる。「風色」という言葉はないだろうが、ホットスブリングスの肌合いやどこかしらしなびた光景はそう形容したくなる。
Hさんと温泉がどのようなものか確かめてみようということになった。決して、温泉に浸かるといった「温泉気分」を前提にしえないのは、ホットスプリングス=温泉ではないことを予感しているからである。メインストリートにはバスハウスと書いた建物がずらりと軒を並べる。バスハウスはいずれも大きく、日本の破風を思わせるような屋根付きで二階建て(に見える)が多く、いかめしい感じがする。フレンチコロニアル様式かどうか定かではないが、レンガ造りや石造りが多くほとんどが白い壁であった.クリスマス間近なのにその気配さえないと思われるほど飾り気のない質素な通り沿いに車を停めて、バスハウスの一つに向かった。玄関へ通じる階段を上がってドアを開けると、驚いたことに日本の銭湯を彷彿とさせる番台ならぬ受付があり、首にタオルを巻いた短パン姿の掃除夫と思われる男性と話し込んでいた白髪の老女が笑顔をこちらに向けた。彼女の後ろには、それこそ緑色をした蓋付きの仕切棚がずらりと並んでいたのである。一つ一つの仕切には白いゴム製の紐付き鍵が付いており、一目でそれが貴重品ボックスであること、そして鍵を手首に巻いて風呂に入ることが了解できた。彼女はまるでその棚の色とコーデイネイトしたかのように緑色のセーターを着てハイネックの綿シャツの白を引き立たせていた。Hさんがすかさず"Nice Sweater"とお愛想を言う。お上手の下手なポクは側で気恥ずかしく思ったが、老女の笑顔に輝きが増した。Hさんが続けて中を見せてもらえるよう頼み込む。彼女が快諾したことは言うまでもない。こうした会話はごく日常的なやりとりに過ぎないが、彼のささやかな「交渉」のリズム感は、アレグザンダー、テネシー州知事のニッサン誘致からヴァンダービルト大学日本人会のスポンサー交渉まで関わった彼の「外交官」手腕を充分伺わせるものであった。
こうして番台のおばあさんに案内された銭湯であるべき場所は、その期待に反してバスタブのずらりと並ぶそれであった。一つ一つのバスタブは灰色の大理石模様の衝立で仕切られており、そのままバスルームを連想させるものであった。幻滅のあまり明らかにボクたちの声のトーンは下がっていたが、それでも" How nice"とだけは付け加えることを忘れなかった。「また、後で寄ります」と決して戻ることのない挨拶を残してその「銭湯」を後にした。建物の裏手に湯気の立ち上る元湯があったが、それも湧き水のように出ているだけであった。それを目の当たりにしたのを最後に「ホットスブリングス」はホットスプリングスに戻つていた。
車に引き返してから近くのバーガーショップ・アービーズでローストビーフ入りのハンバーガーとコーヒーをテイクアウトした。途中で当初の目的地であったホットスプリングス国立公園を過ぎたが、すでにそこを楽しもうという気分ではなかった。このあたりはウィチタ国立保護林区をはじめ南部の豊かな森林に囲まれた地域である。ブロイラー小屋らしき建物や赤く塗られたサイロをもった農家が時折過ぎる。12月にしては暖かい日で、車の窓を開けると、風が音を立てて入り込んできた。ボクは腕を伸ばして手の平でその風圧を感じた。腕に沿つてかけ登つてきた風が髪を引き剥がそうとするのが、フェンダーミラーに映じていた。
しばらく前に買ったオムニバス・カセットの"Emotions"をラジカセにセットした。ダン・ヒルの「サムタイムス・ウェン・ウイー・タッチ」、ボール・デイビスの「アイ・ゴー・クレイジー」・・・など1、2年前に流行つたアダルト・コンテンポラリー (ソフト・ロック)の曲が木立の流れに溶け込んでいく。余りにもロマンチック過ぎてHさんが「やっぱりこれは夜にしましょう」と言うのにうなずいた。「・・・this one's for you」バリー・マニロウはいきなり歌いやめるはめになった。いつの間にか木立も途切れ、テキサス米や綿花の畑が広がるようになっていた。
ホットスブリングスから2時間しないうちにアーカンソーとオクラホマの州境にあるフォートスミスの先で40号線に戻つた。星の形をした目印の付いた10メートルはあろうかという巨大な板に大きくオクラホマとある州境表示を通り過ぎてHさんと顔を見合わせた。彼はブレーキを踏むとそのまま200メートルほど車をバックさせて戻つた。もちろん二人で記念撮影をするためである。日本でならわざわざ県境で写真を撮ることなど思いつきもしないが、荒野の道ばたに設置されたその大きなヲンドマークは無邪気さを引き出す働きをした。運転を替わってハンドルを握つて気づいたが、もう周りに緑はなかつた。右手の黄土色の水平線に煙が見える。その煙がその荒れ果てた地形の舞囲気を盛り上げていた。はるか右に見えていたその煙は、いつの間にかすぐ近くに来て、枯れた茶色い低木林を広く焦がした場所を指し示していた。道路脇には消防車が何台か黄色い緊急灯を付けたまま停止しており、その場のあわただしさを強調していた。
その火災現場をあとにすると、景色全体が薄茶化てきた。乾いた日差しが車の歪んだ射影を作るのに気づく。まだ陽は高かったがエンジンのハミング音とその影の変化の様子だけがモノクロームの背景の中では明確な縁取りを持つていたのである。オクラホマシテイーまでもうすぐであった。
つづく