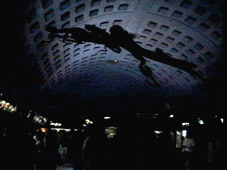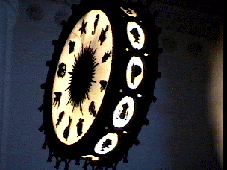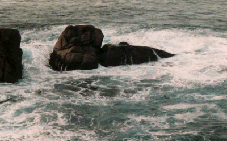福本謹一


ボクがまだ子どもという言葉を背負い、家族の中に位置づけられて旅行をしていた頃、水族館は、水族館でしかなかった。水族館をなぜ「魚族館」でないのかなどと考えてみたこともなかったし、遊園地との同義語的な意味あいしかなかったのである。隣の見知らぬおじさんの「この魚、うまそうやな」という言葉にフンガイを覚えたのはずっと後になってのことであった。
水族館が、アクアリウムとして、特別の意味をもつようになったのは、シカゴにあるシェッド・アクアリウムを訪れたときからである。この水族館は、1930年にマーシャル・フィールド・デパートの名誉会長ジョン・G・シェッドが320万ドルを投じて建設したものである。ミシガン湖のほとりに位置したこのアクアリウムは、今で言うウォーター・フロント開発のはしりとして登場した。グラハム、アンダスン、プロブスト、ホワイト合同設計事務所が担当した古代ギリシャ風の建物は、どこにでもありそうなクラシックな外観をもつものとして見過ごされ、ややもすれば、対峙する現代建築のパノラミックな摩天楼に気を取られて、チケットを買いに並ぶ行列の中で、熱帯魚のことしか考えなくなってしまう。しかし、ドリス式柱頭を見上げてペディメント(正面小壁)の先の鬼瓦様のアクロテリオンに眼をやると、貝を糢った文様の中に鯨のレリーフが見える。2ドルの入館料を払って、中にはいると、広いロビーになっている。ロビーを抜けて中央奥に進むと珊瑚礁を再現した円筒形の水槽に出会う。そのまわりをカリブ海、インド・太平洋、北極・南極海、五大湖周辺、アメリカの淡水魚、南米・オーストラリアの淡水魚、アジアの海の7つのセクションが放射状に別れ、真っ暗な館内に光のジオラマが無数に浮かんでいる。余程眼をこらさなければ、巨大タコが暗い天井を覆っていることに気づくこともない。最大水槽の規模から言えば決して全米一ではないが、800種8000点という「水族」が210の小さな空間にひしめき、「観魚室(うおのぞき)」という明治の訳語にふさわしい幻想的なパノラマになっている。もう一度やや明るいロビーに戻れば、そこが幻想と現実をつなぐ巧妙な装置であることがわかってくる。天井の成型スタッコ(しっくい)には、組み紐や円花飾りの代わりに巻き貝や亀がレリーフされており、シャンデリアは、ウニを糢った触足の先に電飾が施され、その内側には、海の生物がいくつも描かれている。入口に近いところに立つランプスタンドは、オウム貝を模したステンドガラス・フードがついている。ここでは建物自体もアクアリウムなのであり、水生動物のサンクチュアリーへのトランジショナル・ステージなのである。そこには設計者の徹底したこだわりが感じられる。そのこだわりと静謐感と透明感に溢れた館を出ると、シカゴの現代建築の眩しいスカイラインがミシガン湖の湾曲線と交わる。そこにもまた非日常的な幾何学的空間がある。浦島太郎の感覚を味わうことのできる瞬間である。
このジョン・G・シェッド水族館に足を踏み入れて以来、ボクのアクアリウム探訪が始まった。アクアリウムは、ヨーロッパでは、19世紀後半に建設が集中する。このアクアリウム・ブームの火付け役となったのはイギリスの博物学者P・S・ゴッスであった。彼は、四面を板硝子で囲んだ水槽を試作し、水中生物を横の視点でとらえることに成功した。時はあたかもヴィクトリア時代中期(1850年頃)。彼は、この水槽をアクアリウムと名付けたのである。アメリカでは、ニューヨーク水族館が、1896年に最初のアクアリウムとして登場した。現在のウォーター・フロント開発のはしりとしてアクアリウムが中核的役割を担ったのは、ボストンのニュー・イングランド水族館(1969)である。ケンブリッジ・セブン・アソシエイツという建築家及びデザイナー・グループがその設計を担当した。この事務所の主任設計者であるピーター・シュマイエフは、1981年にボルチモア水族館、1990年に大阪の海遊館を手掛けている。
ニュー・イングランド、ボルチモア、海遊館の水族館は、いずれも巨大な水槽を中心に、まわりをスロープが取り囲み、海面から海底までの生物の生態を立体的に見せる。幾分3館には、色合いの違いこそあれ、テーマパーク風の作りは共通する。実際に、訪れてみればわかることだが、巨大水槽という海中環境の再現に力点を置くあまり、一点豪華主義的な印象をぬぐい去ることができない。ニュー・イングランドが499種、ボルチモアが495種、海遊館が400種と生物の種類では、シェッド水族館の足元に遠く及ばない。この種の数は、アクアリウムの「幻想パノラマ」を演出する重要な鍵になる。海遊館などは、ブロードウェーの舞台照明家にまで照明演出を依頼したにしては、規模の割にも種の数が少ないこともあって、変化を感じ取ることがなく、失敗に終わっていると言っても過言ではないだろう。ボストンと海遊館は、マーケット・プレイスというショッピングモールが控えているが、日常にすぐさま引き戻されて、アクアリウムが日常なるものの延長であることを実感させられる。もっとも、ニュー・イングランド水族館は、1995年に移転し、最大水槽が、海遊館の2倍の規模を持つ巨大アクアリウムに生まれ変わる予定で、評価は変わるかもしれない。
新潟のマリンピア日本海、品川区水族館、登別マリンパークは、水中トンネルをして、それこそ水族を下から見上げる視点を提供する。それぞれがそれなりに地方の特色を生かしたテーマを設定して水族館の再生にのりだしたものである。しかし、いずれも規模が小さく、コンセプトの脆弱さものぞかせる。
カリフォルニアのモンタレー・ベイ水族館(1984)と鳥羽水族館(1990移転)は、外観もその地理的位置づけも類似したものがある。モンタレー・ベイ水族館は、サンフランシスコから車で約3時間。モンタレー湾に位置する。モンタレー、カーメルといったリゾートに近く、有名なペブル・ビーチ・ゴルフ・リンクスもすぐそばである。鳥羽水族館は、大阪、名古屋から3、4時間。志摩国定公園に近く、志摩半島を望む鳥羽カントリー・クラブがあるところまで同じ。モンタレー・ベイ水族館は、カリフォルニアの近海に生息する巨大海藻ケルプを入れた水槽とラッコが売り物である。しかしここではむしろ砂浜を再現し、小型の水鳥が手の届くところで遊ぶ空間にオリジナル性を感じることができる。一方、鳥羽水族館は、ラッコ、ペンギン、イルカと3種の神器はもちろん、大型水槽底部に張り出したアクリルガラスの展望室をもつ。環境破壊を考慮して55種650個の人口珊瑚の制作をアリゾナのメーカーに依頼した。展示種では、400種と、海遊館と同じだが、展示数が70000点と、海遊館の2倍であることと、海遊館の様にスロープによって観賞者の流れが規制されておらず、変化を楽しむと同時に、主体的な「間」を保持できる。「うおのぞき」趣味とストーリー性を持たせた水生環境のプレゼンテーションが程よくマッチしたアクアリウムである。
葛西臨海水族館は、ピーターシュマイエフとハーバード大学建築学科同窓の谷口吉生があたった。マグロが回遊する大水槽が売り物で、ガラスドームを見ているとずいぶん開放的な気分になる。東京湾の景観のなかに建築の自己主張がのぞく。「うおのぞき」の時代から水族と地続きの関係性を強調する時代なのかも知れない。しかし、だからこそ、アクアリウムとしては、失望してしまうのかも知れない。
アクアリウムが誕生して150年。「珍奇性」から「環境」へとキーワードは変化したかも知れないが、最近の水族館ブームは、結局は「通人や幇間芸者を引き連れて見るのも同じすい族の館」(風俗画報、明治40年)と同じ類かも知れない。
・・・モンタレー・ベイの強烈な印象は、今も脳裏に焼き付けられている。「幻想のパノラマ」などそこにはなく、共感覚的な自然のうねりがあった。スケジュールのないラッコの黒い動きは、アクアリウムにわざとらしい環境をもちだすことなどとは無縁のように白い渦と格闘していた。
(実際の水族館訪問を元にしたものですが、水族館の一部の情報については、情報誌「サライ」を参考にさせていただきました)
2009年に再度シェッド水族館を訪れる機会に恵まれたが、以前と違い、学習が全面に出て、ビジュアル解説がやたらと増えたことや、トランジショナル・ステージでもあった玄関ロビーにはカフェを配置し、水族館への入場を前提としないでもファーストフードを利用できるようにするなど、市民への開放的な期間であることを強調するものになっている。反面、こうしたアプローチが本来の建築と水族館としての連続性を喪失させるものとなっていることは悲しい。