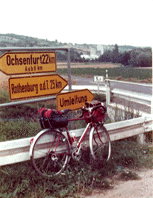Europe in Retrospective
その4

福本謹一
7月14日に羽田を出発してすでに2週間あまりが過ぎた。ミュンスターでペンパルの家にホームステイした後、サイクリングを開始した。ヴュルツブルクからフュッセンまでの街道はロマンチック街道と呼ばれ、中世の諸侯の城壁で囲まれた街を結ぶ・・・1973年の夏は浪漫的な光彩を放ちはじめようとしていた。残りの5週間はあっというまだ。
ヴュルツブルクを出発してもすぐにはロマンティックな街道を走っているという実感はない。道ばたに小さく立つロマンティッシュ・ストラーサという表示に自己満足する。それがなければただの田舎道である。道はなだらかに続く。農家の子どもたちがトラクターに藁積みを手伝う姿が見える。行き交う車は少なく、本当にこれがその街道であるのか不安がつきまとう程であった。しばらくして、ジェット機の金属的なエンジン音が迫ってきた。次の瞬間には2機の戦闘機が前方の田園風景を切り裂いた。その先鋭的でジュラルミンそのままの機体からしてアメリカ製のロッキードF104であることは明らかであった。一度視界から消えた2機はすぐさま低空でボクの方へ正面から迫ってきてアッと言う間に轟音を残して消えた。しかしその2機は後方で旋回して今度は背後からこちらに迫ってきた。ひょっとして撃たれるのではないかという不安がよぎり、思わず身を屈めてしまった。まるでこちらを標的に訓練をしているかのようであった。その後低空で道の前方を横切る際に西ドイツ空軍であることを示す黒い十字のマークをはっきりと見せて飛び去っていった。東ドイツとの国境まで直線で約70キロ、チェコまで約200キロの地点である。しばらくして後ろから陸軍の兵員輸送トラックが何台か通りすぎて行った。トラックの後部はいずれも開け放たれていて灰色の軍服を着た陸軍兵が10人程度乗っているのが見えた。最後尾のトラックの兵員に向かってこわごわ右手をあげた。すると、端に立っていた一人が表情を変えずに手をあげて応えた。他の兵士も2、3人がこちらへぼんやりとした視線を向けた。グレーの制服とその無機質な視線。社会科の教科書にあった「東西の緊張」は、ここでは括弧付きではないのだ。
ヴュルツブルクからローテンベルクまではわずか40キロ。2時間ほどの距離である。ロマンチック街道は真剣に走れば三日で抜けてしまいそうであった。しかしローテンベルクやディンケルスビュールを見ない手はなかった。11時を回った頃、まさに忽然とローテンベルクの街の赤い屋根が見えてきた。中世の城壁に囲まれた街はなだらかな緑の田園の中に禁欲的なたたずまいを見せる。農村と街との決別が色の対比としてもあからさまになっている。街に入ると急に自転車がガタゴトし始めた。その肩に伝わる振動が街のメタファーとしての石畳を覚醒させた。
しばらくしてその石畳の遠近法の奥に自転車に乗った4人のグループが目に入った。自転車にはサイドバッグがつけられている。ドイツ人ではなさそうだ。彼らが数十メートルに迫った所で「アッ」と声をあげた。ミュンスターを出てそれこそはじめての発声だった。そこにはなじみの顔、日焼けしてはいるが確かに先輩たちの顔があった。彼らもこちらに気づいたのか、「なんやー、こんなところで。誰かと思えば・・・」「生きてたんか、おまえ」ローテンベルクの通りの真ん中で日本人たちが日本語で大声を上げた。まさか途中で先輩たちに出会うとは思いもよらなかった。ベルンで別れて互いにどこに行くのかという予定すら聞いていなかったので、全くのハプニングであった。彼らはチューリヒから南ドイツに入りそこから北上してロマンチック街道に入ったとのことであった。ロマンチック街道は浪漫的と記述されることで、その瞬間的体験や偶然性を讃えるものとなって、ボクたちの再会を情感的なものにしたのである。
とりあえずユースに落ちついて情報交換をした。ローテンベルクのそれは、二つの屋根裏部屋の窓がちょうど人間の目となって建物全体の外観を人間の顔のようにみたてさせる。前庭で管理人の小学生の娘とトランプに興じてからローテンベルクの時計台など観光に出かけてその日をすごした。
翌朝、先輩たちは北へ、そしてボクは南へ向かってまた一人になった。ディンケルスビュール、ネルドリンゲン、ドナウベルトと、田園を点で結ぶ中世の街はいつも忽然と現れた。道ばたにキリストの十字架が点在する。浪漫街道はその響きとは対照的に宗教的匂いを放っているのだ。街道筋のユースはどこも小さく、日本人と一緒になることはなかった。アメリカ人の家族といっしょにゲームで騒ぐこともあれば、それこそ他に宿泊客のいないこともあった。
アウグスブルクに入って急に予定を変更することになる。このまま行けば、あと100キロほどでノイシュバンシュタイン城のあるフュッセンに着く。ミヒャエルさんにも約束していたことである。しかし、ふと、このままノイシュバンシュタイン城を見れば、今回の旅行がそこで終わりになりそうな気がした。その目的を達成すればヨーロッパを全て見たような錯覚に陥って二度と世界を見ることもないのではないかとなぜか追いつめられたような気になった。確かに高校時代からドイツ、ドイツとあこがれてドイツ中をくまなくサイクリングするはずではあった。しかし、地図には、ドイツの隣にオーストリアが、スイスが、フランスが、チェコが、オランダが広がっている。ここまで来てドイツだけにこだわることもないだろうと考えた。
アウグスブルクから東に転進したボクはミュンヘンへと向かう。途中、疲れて道ばたの木のベンチで仮眠をとった。いつのまにか日が暮れかかって、ミュンヘン市内に入った頃は真っ暗であった。ミュンヘンのユースは、いかがわしい連中がたむろしているので利用しない方がいいと聞いていたこともあって、安ホテルを探した。近くの酒屋で2本ミュンヘンビールを買って飲んでみた。甘ったるい黒ビールの味が夏の空気を一層気だるいものにした。
ミュンヘンで美術館を一通り巡った後、オーストリアのインスブルックを経てスイスへ引き返し、ベルンのユースにたどり着いた。そこで2、3日疲れをいやそうと思った。ベルンのユースには日本人が6、7人泊まっていた。その中には、ベルンで働くレストランのコックも二人いた。アパート住まいらしいのだが、日本人との情報交換が目的だと言う。彼らは饒舌であった。どこのユースがいいとか、イタリアは危ないから気を付けろといった旅行ガイドから、どの通りに娼婦が立っているといった危ない情報まで「ウブな」学生たちに彼らの親切さを発揮してくれる。しかし、わざわざ日本人と一緒にユースに泊まる姿に彼らがかかえる「疎外感」を見たような気がする。彼らは「旅行者」ではなく「外国人」なのだ。
スイスの山並みにはツンととりすました美しさがある。インターラーケン・オストのユースで一緒になったノルウエーの女子大生アンナ・リサと一緒に近くの湖にハイキングに行った。彼女はバックパッカーの一人で、オレンジ色のフレーム・パックを背に旅行していた。アメリカやヨーロッパの放浪学生は大抵、国旗のワッペンを縫いつけたフレームパックとベルトに布製ではがき大のウエスト・バッグをしていた。それがひとつの「スタイル」を形成して世代の価値を共有する装置として機能していた。昼飯にはブールというパンと桃と牛乳を調達して持っていった。彼女はその桃を皮をむかずに食べ始めた。日本の桃のように産毛がないせいもあるが、文化はどこまでも違うのだと感心する。湖は8月だというのに冷たかった。そこでは時間の階調が波紋にあわせて微妙に変化していた。
ベルンに戻ってユースで大阪外語大学4年のSさんと知り合う。彼からフランスとスペインに足を延ばしてみないかと誘われて、自転車をたたむことになった。ベルンを夜行列車で離れ、ディジョン、リヨンという地図でしか知らない街を過ぎていった。ディジョンで飲み物を買いに二人で降りた。ストラスブール行きの列車がすれ違う。大きなベレー帽をかぶったフランス海軍兵の白い制服が駅舎のライトの中でまぶしく光る。彼らは、ホームの女性を見つけると大声で歓声をあげ、口笛を鳴らした。列車に戻ると、2等車は一杯になっており、ボクたちは1等のコンパートメントの通路で寝ることになった。最初自転車を背中にしていたが、いつしか床に寝そべっていた。列車はパリ駅に静かに入構した。どこを見てもフランス語であった。フランス語圏への旅行が予定外だったこともあって、Sさんだけが頼りだった。彼はフランス語専攻ということもあって、足どりも軽やかである。その足跡をたどるようにとぼとぼと輪行袋をかついだボクが続く。パリは地下鉄の街だ。複雑な路線が色分けしてこぎれいなデザインに仕上げてあったが、結局文盲にはその図も不安をかきたてるシュールな絵でしかない。
ルーブルのモンナリーサもエッフェル塔もモンマルトルも主体性のない旅ではリアリティを持たないことを知った。カルチェ・ラタンの安宿にはバスタブはなく、隣の部屋のイラン人の親娘と譲り合ってシャワー室を使った。安宿は最初から安いユースとは意味が違う。安さの所以があり、窓から望む遮断された空間が閉塞感を助長する。しかしそれは弁明にしかすぎない。パリになじまないというより、適応力が欠如していることを痛感した。変化に対応することが苦手なのである。Sさんはちょこちょこ歩きまわってはいろいろな情報を集めてくる。ボクはさながら親鳥に餌をせがむ雛鳥そのもののようであった。どうもまずいなと思いつつもスペインまでは従うしかない。
夏のパリは外国人、とりわけ中近東からの移住者の街のような印象を受ける。彼らは口論し、道ばたを掃き、コーヒーを運ぶ。彼らのしたたかな生き様はパリのエスプリやアンニュイさを陰で支える。そんなパリを後にスペインへまたしても夜行列車で向かった。Sさんが席を探してくると行って、荷物まみれのボクを置いて先に行く。しばらくしてSさんが顔を上気させて「かわいい娘がいる席があったよ」といって戻ってきた。行ってみると確かにそのコンパートメントには高校生くらいのかわいい女の子がいて互いに自己紹介した。だが、すぐに「パパと一緒に旅行しているの」というミッシェルの答えにSさんが「なーんだ」と日本語でしょぼくれた。しばらくして「パパ」が飲み物をかかえて帰ってきた。話してみると彼はインドネシア大使館に勤める外交官であった。「夏休みをもらって娘と帰国したんだ。これまでベトナムのことで大変だったんだ。以前はわが国も戦ったし、次はアメリカ。ベトナムとはインドネシアの外交チャンネルが結構利用されているからね・・・」話はそれ以上あまり進まなかった。アジアから帰ってせっかくの休みにフランス国鉄の列車内でまたアジア人の顔を見るなんて思いもよらなかっただろうにとボクは思った。彼らは暗いトゥールーズで下車した。
国境でスペイン税関を通る。ふらふらしながら、乗り換えに急ぎ、ステップをあがる。フランス国鉄は広軌、スペイン鉄道は日本と同じ狭軌のため列車はそのまま乗り入れることはできない。また暗い廊下にふたりして寝ころんだ。しばらくしてなんだか様子がおかしい。フランス国鉄の制服を着た車掌が回ってきた。「パリ?」と僕たちに尋ねる。「ノン!マドリ!」ととっさに反応した。車掌は親指を進行方向とは逆に指すのだ。「エー!」と二人で顔を見合わせてあわてた。パリに戻ろうとしているのだ。ともかく最寄りの駅で降りることにした。税関まで通ってまでまちがえるとは思いもよらなかったが、ともかくスペインのマドリッドについたのは半日遅れだった。駅に着くなりSさんが民宿を探そうと歩き出した。一時間ほど歩き回って民家の2階の一室を貸す所に落ちついた。家の中には洗濯ロープが張られ洗濯物がつるされたままで、子ども二人におばあちゃんもいるところだった。おぼえ立てのスペイン語で挨拶したが、反応はない。それっきりボクらもだまってしまった。荷物だけを置いて、夕方からフラメンコを見せる酒場を探してその宿をでた。小さなレストランの前でフラメンコの看板を見つけて入った。赤いドレスの女と黒の服の男のダンサーが客の間で踊る。カスタネットにフラメンコ。スペインを実感させるにはあまりにも公式的すぎた。
次の朝、プラド美術館を手始めに町中を探検する。ボクたちを見ると「チノ、チノ」と子どもたちが叫ぶ。どうも中国人と思っているらしいのだ。別に中国人と間違われてもかまわないが、何となく侮蔑の響きを感じて急にスイスが懐かしくなってきた。路地は暗くて建物は古い。パリのカルチェ・ラタンの下町も同じだった。「チノ、チノ」は至る所で聞いた。それを聞く度に生活感を感じるというより、複雑な気分になった。スイスではハイキングしていてもそこかしこで、人々が挨拶をする。確かに気持ちいい。しかしよく考えれば、スイスは観光国家なのだ。スイスの日常に生活感はない。訪れるものを夢見心地にさせる。今から考えれば、ディズニーランドと同じなのだ。国全体が夢の世界へ誘うマニュアルに従っているのだ。ボクの意識の中にも生活を肌で感じるというより、観光気分が蔓延していたにちがいない。バスでの団体旅行よりはましかもしれないが、本質的には変わらなかったのかもしれない。「自転車」は自己弁明の道具であったのだろうか。
翌日、Sさんはグラナダへ行くと言って、朝早く別れを告げた。民宿のおばさんは相変わらず無口だった。スペイン語も分からず一人で街に出た。心細い。朝飯を食べようと歩き回るが、まともに店は開いていない。何しろ、中欧と違って生活時間帯が2時間ほどずれているのだ。昼飯は午後2時頃から、夕食も午後8時頃からということだ。しかたなくプラド美術館近くの公園のそばの露天で鰯のホットドッグとコーラを買う。「ウノ・コーラ」だけは覚えた。レストランはメニューが読めず、こちらの腹時計とも合わない。3食とも結局鰯になった。神戸の下宿先のザビエル育英会が運営する学生寮の舎監はスペイン人のペニュエラ神父であったが、彼には何と言って帰ろうかと思案した。あまりいい思い出がないのだ。英語もほとんど通じない街で危機感すら感じ始めていた。とにかく歩いた。「チノ」も相変わらずだ。寝台車でスイスに帰ることにした。
スイスでもう一度自転車を組んだ。スイスは美しく、ほっとした。「日常とは何であろうか?」エジプトにも、ミュンスターにもベルンにも、パリにも、マドリッドにも日常はあった。それぞれに異質である。そしてこちらの精神状態によってもその日常は変化する。日常を忘れるように山へ向かった。ツェルマットまでは苦しかった。というよりただなだらかに長く坂が続く。六甲山や雪の北陸道のトレーニングのことが思い起こされる。マッターホルンが見えてもツェルマットは遠い。1リットルの牛乳を飲み干してそのまま寝てしまったこともあった。ようやくツェルマットに着くと、山羊が道をふさいでいる。ここでは車は乗り入れ禁止である。純粋に環境のための交通規制なのか、観光のための環境保護なのかどうかはわからない。ツェルマットのユースは、街からまだ坂道を1キロほど行ったところにあるという。もういやになった。自転車を駅の自転車置き場に残す。すぐそばにライフル銃が無造作に立てかけてあった。その銃に見入っていると戻ってきたスイス民兵がその銃を見せてくれた。一瞬ためらうが、銃がもつある種の魅力には勝てなかった。結構重い。好奇心がすうっと引いていった。「ブランクだ」と彼は言った。弾奏には緑のテープが巻いてあり、空砲だった。「ちゅう・りつ・こく」。夢の国スイスのもう一つの顔をようやく実感した。
それから徒歩でユースまで行った。そこで唖然とした。自転車が30台ほども停めてある。しかも、マッドガードに日本語が書かれていた。「京都大学サイクリング部」。思わず「チノ野郎!」と侮蔑と畏敬の入り交じった声で叫んでしまった。
ツェルマットのユースは日本人だらけだった。ユースの管理人はスイス人だが、奥さんは日本人。数年前ここのユースに来てそのまま結婚して居着いたのだそうだ。「ここは日本人村って言うのよ」とその奥さんはくったくなく話す。二人のドイツ人のBG(今で言うOL)が居心地悪そうな顔をしていたので、食堂で同席した。シュトゥットガルトから来たと言う。彼女たちはまさかスイスのユースで日本人たちに囲まれるとは予想だにしなかったに違いない。部屋ではフランクフルトから来たアメリカ人の高校生マークと大阪のトラック野郎Tさんと一緒になる。マークは貿易会社社長の息子でマッターホルンでヘリスキーをやるという。アメリカ人はやることが違うなーと感心した。
翌日、マークを途中まで送ってからTさんとマッターホルンの向かいのゴルナーグラートに登ろうということになった。マッターホルン北壁が時間と共に色合いを変える。ゴルナーグラートも途中まで山小屋などがあったが、次第に険しく、残雪というか氷河が見えてきた。靴は普通の革靴で裏はサイクリングのフラット・ペダルに合わせて滑りをよくしてある。とても登山できるような代物ではない。氷河を迂回すれば時間がかかるし、氷河を上がれば頂上近くまで早く行けそうだった。Tさんと氷河を抜けることにした。所々に小さなクレバスがあるが、斜度はそれほどではない。木の杖で堅くなった雪をたたいて足がかりを作って進む。上方に見える稜線に登山グループが見えた。一時間ほど登ったところで足を滑らせた。一瞬のことで、岩肌に引っかかって上を見上げてはじめて30メートル程滑り落ちたことがわかった。やはり革靴では無理であった。氷の上をただ滑ったせいか身体に痛みはどこにも感じなかった。起きあがろうとしたら、先に行っていたTさんが「動くな」と言ったまま少しずつ降りてきた。助けに来てくれるまで時間がかかった。ひっかかった岩の谷側にクレバスがあったのだ。ようやく横に来たTさんに杖を渡して引っ張ってもらった。降り際にクレバスを端からのぞく。小さいけれど、はまれば出てくることは不可能なようだった。内側はメロンシャーベットのような美しい緑色をして、かなり深そうであった。氷河がかなり厚いことが分かった。結局これ以上登ることはあきらめて下山した。絵はがきには、マッターホルンの美しさだけを強調して日本へ送った。
翌日ブリークへ戻って、ローマのテルミニへ向かう列車に乗った。もう旅行も終わりに近づいていた。テルミニには駅舎という意味と終着地という意味がある。実際、列車を利用するのはこれが最後となり、ローマはまさに終着駅となった。コンパートメントにはオーストラリアの女性バックパッカー二人が入ってきた。メルボルンの女子大生であった。3人だけだったので、みんなで足を向かいの座席に投げ出してくつろいだ。ローマに着くのは翌朝になる。最初は話をしていたが、互いに疲れているせいか、いつしか話をしなくなってそのうち眠ってしまった。
ヨーロッパの中央駅というのがだいたいそうであるようにテルミニもホームが横並びになり、19世紀の印象派の絵画に残されている駅舎の風景と変わりはなかった。二人に別れを告げてから、日本航空のローマ支店の前に急いだ。出発前に決まっていた集合場所である。すでに先輩たちの姿がそこにあった。T先輩たちとはローテンブルク以来の再会である。ローテンブルクでの予期せぬ再会があったせいか、今回は淡々とした挨拶で終わった。フランスやスペインを一人で放浪したK氏のフレームパックは薄汚れ、各地のワッペンが所狭しと貼ってあった。武勇伝が聞こえてきそうだった。女性軍はやれイタリア男がうるさいのとかどうとか言っている。みんながそろったところでエジプト航空に勤めるM氏が予約していたペンシオーネ(ペンション)に向かった。日本の旅行者がよく使うのか、そこのオーナーのおかみさんは、これは誰それに描いてもらった絵だとか、いろいろと日本びいきをアピールする。食事は外へ出て、パスタを食べることになった。セルフサービスの店でスパゲッティーとコーラとサラダを注文する。ともかく安かった。これならイタリアに早く来ればと思った程である。イタリア人はスパゲッティーをフォークでくるくると目に止まらぬ速さで巻いては口に運ぶ。芸術的な光景だ。真似ようとしたが、フォークをスピンさせることは不可能であった。
翌日の和製「ローマの休日」は、ロマンス抜きの観光である。トレビの泉でコインを投げ、スペイン広場の階段にたたずみ、帝国時代の水道をたどり、円形競技場で古代を偲ぶという具合に型どおりの過ごし方をした。
ローマからはブリンディジという港へ出て、アテネに向かい、そこからカイロに飛んで再びエジプト航空で東京に戻ることになっていた。しかし、船でアテネに向かうには時間がなさ過ぎた。ローマの学生ユニオンで格安チケットを探すことになり、結局今はなきスカンジナビア航空(SAS)のローマ=アテネ便のチケットを手に入れることができた。ローマ発のSASは各国の放浪学生たちでいっぱいで、タバコの煙が狭い機内にたちこめていた。ボクたちは背の低い美人ステュワーデスにとりこになって1時間あまりを過ごした。
アテネ空港はオリンピック航空という機体がせめぎあっていた。オリンピック発祥の地ギリシャらしいネーミングである。その日はアテネ市内の東京ハウスというまるで浮浪者の巣のような所に泊まった。放浪学生がほとんどなのだろうが、ヒッピーまがいの連中も多い。二日目T先輩とアメリカ人のツアーバスに入れてもらって市内観光をした。年輩のアメリカ人が多い。アメリカ人はここでも「外人」である。先輩は風貌が「外人」なのでアメリカ人の中でもそれほど違和感はないが、ボクは見るからに「外人」なのであった。異質の中の異質。変な感じであった。英語のガイド着きツアーだが、時間に追われて結構忙しかった。団体旅行はどこも同じである。
アクロポリスの丘に立つアテネの神殿の遺跡には存在感があった。かつてのくずれたコラム(柱)はすべすべしており、大理石の感触と歴史を実感させる。丘から望むアテネの街は決して近代都市ではない。丘の上と下界に歴史的時間のすれ違いを感じさせるものは少なかった。遺跡という時間のメタファーはここギリシャでは現代のコンテクストから切り離されてはおらずグラデーショナルに溶け込んでいるのだ。神殿内の博物館では古代ギリシャ時代の装飾品などが展示されていたが、その美しさと技術的洗練さに圧倒される。古代は決して陳腐でも未熟でもない。
翌日、リコンファメーションを忘れていたこともあってT先輩たちは航空会社の支店へ行くついでに観光をすると言って出かけた。ボクとY氏とJ君の3人はスニオン岬までバスで泳ぎに行った。このスニオン行きはギリシャの神々のちょっとしたいたずらにもてあそばれることになる。
スニオン岬まではバスでほんの一時間半ばかりである。土地の人に観光客が乗り合わせたバスは砂埃をあげて南下した。海に近づくにつれて木が少なくなる。荷物を抱えたギリシャのおばさんたちの顔にうっすらと汗が浮かんでいる。小さな神殿が見えてスニオンに降り立ったのはボクら数人だった。そこでボクたちは言葉を交わすことを忘れていた。赤紫色のエーゲ海が崖の向こうに広がっていたからだ。「海は緑」ではなかった。バスが走り去った後に潮の匂いのする風が静寂を運んできた。ボクらはその風の来る方へ細い道を見つけて崖を下った。エーゲ海がワイン色から深紫に変わって輝く。右手の崖の上に先ほどの神殿風の建物が小さく、しかしくっきりと青緑色の空に浮かんでいた。何世紀も前トルコ海軍を威嚇する前哨塔だったのだろうか。
海はあたたかかった。紫色の海は顔を沈めるとクリスタル・クリアーに変わった。こんなに海が美しいと感じたことはなかった。2、30メートル先まで海底が見えた。あまりに見えすぎてある種の恐怖にとりつかれる。海の女神サイレンに引き込まれそうなのだ。水際からすぐ数メートルの深みになるために足は届かない。同じ岩場でも日本でならすぐ不透明になるはずの深さなのに海の生物がくっきりとうごめくのがわかった。別の岩場をまわると小さな砂浜が見えたのでそこまで泳いだ。他に人影はない。砂浜を波音が駈けていく。エーゲ海の向こうにアルプスをコラージュしたくなった。
アテネには午後も遅くなって戻った。東京ハウスでボクたちを待っていたのは先輩からのメモであった。メモは手帳を破って3枚にわたって殴り書きしてあり、それが今も残っている。
「今日エジプトエアーに行ったが、驚いたことに明日の便はキャンセルになっていた。我々は海まで探しに行ったが見つからなかったので、しかたなくカイロへ21:20発のMS776で発つことにした。もし、君たちが9月2日カイロ11:45発の機に乗ることができれば幸いだが、それができないときは一週間遅らせて来週の木曜アテネ発の便で帰る必要がある。2日カイロに行くにはオリンピックが安いと思われる。金とチケットをおいて行くから君たちで何とかしてほしい。たとえ木曜の便ででも、カイロ東京間が問題だと思う。できれは2日発に間に合うようにしてほしい。最悪の場合、東京まで帰ることができなくなるかもしれないが、その時は、テレックスでエジプト航空の大阪オフィスに居所と必要金額を知らせてくれれば帰るための努力はする。今日は、夜8:00にチェックインなので、タクシーで急げば間に合うかもしれない。そちらも最大限の努力を払ってほしい。チケットと金5万4千おいていく。注)福本氏は8/31は東京ハウスにいてください。」
ぼくたちは、しばらく呆然としていた。すでに時計は夜9時をまわっていた。Y氏が「あいつら、よくも俺たちを見捨てていきやがって」と憤る。ぼくは「最悪の場合東京まで帰れなくなるかもしれないが・・・」というくだりの所で頭が一瞬白くなった。1週間も遅れたら、このアテネか、カイロでどう過ごせばいいのかと不安がよぎった。3人で途方に暮れているところへ、東京ハウスのオーナーの「番長さん」が、「もう一枚忘れとった」と今度は大きいノートの切れ端を持ってきた。
「ふくもとさん、あしたのひこうきをあたってだめならエジプト航空に強引にこうしょうしてかえってこい。できるだけ早く日本に居場所をしらせるように ひこううき きょう おくれる 10:15にでるから10:10ころまでにこられたらとばしてこい」
タクシーをとぱしてもとても空港に間に合う時間ではなかった。ひらかなの多さが不安を増大する。「交渉か」とボクはつぶやくしかなかった。
次の朝、エジプト航空のアテネオフィスへ歩いて行った。バス代もけちった。オフィスへ着くなり、キャンセルの理由を迫つた。カウンターの女性はエジプト人かギリシャ人かどうか分からなかったがともかくあのクレオパトラを思わせるアイシャドーはしていなかったし、色白でもなかった。彼女は淡々と「リコンファメーションをしなかったので他の客に回した」のだと言う。そこから、彼女に何をどう言つたかを覚えてはないが、ともかくありとあらゆる苦言をまくしたてたことだけは確かである。興奮していたのかもしれないがすったもんだする内に結局その日のSABENA航空の便に乗れるよう手配してくれることになって3人で胸をなで下ろした。
カイロ空港は東京の地下鉄のように白い衣装を着た人たちであふれていた。入管手続きを済ませて待合室に出るとエジプト人たちの浅黒く鋭い目つきの顔の間にT先輩たちの笑顔があった・・・。
In Memory of My Father
Who Supported My Travel in Europe
ペンフレンドのカリン・ルイスは、その後大学院まで進み、教育学博士を取得。現在(2011)、ボルクスブルクの生涯教育センター教授を経て副所長をしている。