ヨーロッパの青い空
Europe in Retrospective
その3

福本謹一
輪行袋を途中でかついで急いで道路を渡ったせいで少し息を切らした。重量は12.8キログラムと普通の自転車よりは軽いが、それでもフロントバッグとサドルバッグを両手にすればかなりの荷物である。自転車に乗って走っている方がはるかに楽なのだ。電話ボックスには、シルバー・グレーの公衆電話が備え付けられていた。受話器を手にしながら、しばし電話機の色やデザインにみとれた。数字までが日本のものとセンスの違いを感じさせる。カリン・ルイスの電話番号は025014469であったが、どこまでが市外局番なのか分からず、ともかく全部回してみた。ダイヤルの音がコトコトと軽やかであった。すぐさまルルルという呼び出し音がして「ヒア・ルイス」と女の人の声がした。カリンのお母さんのようであった。緊張してはいたがほっとしたものを感じた。「ヒア・キンイチ・フクモト、カン・イッヒ・ビテ・フロイライン・カリン・スプレッ・・・」と最後まで言い終わらないうちに、「ヤー・ヤー・・・」と受話器をふさぐ音がした。軽い咳払いがして「キンイチ?いまどこ?」と小さめの声がした。初めてカリンの声を聞いた。ペンフレンドだから当然のことであるが、筆跡で「カリン」を知っていても、声で認識するのはこれが初めてであった。駅のところにいることを告げると、お父さんと一緒に迎えに来てくれると言うので駅の花屋の前に立つことになった。
20分ほどして、グレーの背広に紺のストライプのシャツを着た「お父さん」と「カリン」が手を差し出してきた。一ヶ月前に日本に送られてきたカリンの写真はミニスカートから伸びた足が長いせいかボクよりはるかに高そうな「カリン」を想像していたので、以外に華奢で背もボクより低いその女の子に驚きを感じながらも「カリン」をカリンとして受け入れるのに時間はかからなかった。お父さんは中肉中背で、髪は黒く風貌はアーリア系と言うより南の方の印象を受けた。お父さんは、威厳を示すかのようなしぐさで自転車の入った輪行袋をトランクに入れてくれた。自転車の重たそうな様子を見て、「大丈夫?」とカリンが手を貸そうとする。そこには「ドイツ人」で なく、「親子」の姿があった。
なく、「親子」の姿があった。
互いにまだ意識しているせいか言葉をあまり交わさなかった。「ここが市庁舎よ」とカリンが指さす石づくりの建物を目で追いながら、自分でもおかしいくらい「ヤー」と声をあげて緊張を振り払おうとしているのが分かった。ルイス家は、駅からさほど遠くはなく、先ほど列車で通り過ぎた新興住宅地の中にあった。自転車に乗った子どもたちが車の中の東洋人を目にしたせいか、物珍しそうに後を追ってきた。停車した先にラベンダー色の平屋があった。カリンが送ってきた白黒の写真の背景とその家が頭の中で重ね合わされて、モノクロームのイメージに色彩が加わって木立のそよぎと子どもたちの歓声が調合された。
中に入ると、お母さんとカリンの妹が出てきて挨拶を交換した。妹のカースティンはまだ9歳で恥ずかしそうにお母さんの腕にすがっていた。カリンが自室へ案内してくれて、ボクの泊まる部屋だと言った。ベッドと作りつけのデスクに小さな黒いデスクライトの置いてあるシンプルなしつらえであった。飾りものは小さな陶器の人形くらいで女の子の部屋にしては簡素であった。カリンは白いベッドスプレッドをたたんでベッドの足下のチェストに入れた。「寝るときはここに入れておけばいいのよ」と言った。それから窓枠のテープ状のものを引っ張って見せた。するとブラインドのようなものが窓の外側を降りてきた。それはブラインド兼雨戸であった。テープの引っ張り具合で細い板と板の隙間が微妙に調整できた。きっちりと閉めると真っ暗になった。彼女にとっては、ごく当たり前の解説だったに違いないが、ボクには、その雨戸は驚異であった。簡単な構造ではあるのだろうが、住まいに対する基本的な関心が日本とドイツとでは大きく異なっていることをみてとることができた。窓は内側のハンドルを回すことで上部が開閉し、好きな角度で固定することができた。日本の住宅でも次第にシステムキッチンだのリビング・ダイニングが住宅の基本設計に取り入れられるようになってきていたが、物真似に長けた日本人がなぜこのような雨戸や窓を実現させえないのだろうかと思った。風に対する強度や網戸との兼ね合いが理由なのであろうか。実はそんな理由などおそらく考えられたこともないに違いない。雨戸なんか見向きもされてはいないのだ。たかが雨戸なのである。しかし、誰かが雨戸から学ぶべきなのだ。
それにしても日本ではデザインという言葉が軽薄な意味でしか用いられていない。デザインはダ・ヴィンチがいみじくも「建築、絵画、彫刻の父」と呼んだように、あらゆるものを構想することを意味していた。明確な目的的意志に裏付けられた「設計思想」だったはずのものが、日本人はどちらかというと表層的な抜け殻の美を信奉することに腐心し、哲学することを忘れ去ってしまったのである。もっとも、基幹産業を中心にした経済哲学とテクノロジーは存在したかもしれない。しかし、住まいには経済学も哲学もそして本当の意味でのデザインもなかった。日本の家屋は「住まう」ことを第一義にしない住まい。住居だけではない。ライン川沿いに目にした1973年型のトヨタ・セリカはヨーロッパでも人気車種であった。しかし、速度制限のないアウトバーンで走ることを前提に設計されたドイツ車は安全対策としてシャーシや側面部の強度に意を用いていた。トヨタセリカが発進速度を強調したスペックを前面に出した広告をしていたのに対して、日本でも人気の高かったフォルクスワーゲン、通称「かぶと虫」は、シャーシの強度や塗装の質、気密性の高さといったものを売り物にしていた。日本の車がスタイルや速度をキーワードにしていたのに対して、ドイツ車は安全と質を選んでいた。「安全に移動し、長持ちすること」を第一義にしたデザイン思想だったのである。
雨戸を開いて、窓がまた開けられると音が「入り込んで」きた。ふとボクは、その取っ手を持ってもう一度閉めさせてもらった。近所の子どもたちの声や空気の匂い全てが遮断されてしまった。家自体の気密性が極めて高いのである。カリンが「居間に来て」と言わなかったらそこで何度も開け閉めをしていたかもしれない。
居間も外壁の色と同じようにラベンダー色を基調にしていた。それほど広くはなかったが、暖炉があり飾り棚にはいろいろな貝やフレーベルのコレクションを思わせるような鉱物の結晶が置かれていた。庭に面する南側は前面ガラス張りで、ガラス戸を開けるとそのまま庭に出れるようになっていた。床の高さと地面とがほぼ同じ高さなので室内が実際よりは広く感じられた。庭の芝生にはパラソル付きのベンチが置いてあり、いかにもくつろげそうな空間であった。
夕食には、ステーキと蒸したじゃがいも、そしてザウアークラウトがでた。ソーセージが出るものとばかり思っていたので、ちょっと意外であった。ともかく家庭料理である。ユースホステルでの食事がみすぼらしかっただけにとにかく感激してしまった。ステーキにかけられたアップルソースが肉の味を引き立てていた。
夕食後に皿洗いの手伝いをした。オフ・ホワイトで統一されたキッチンは小さかったが、調理した後が感じられないくらい片づけられてあった。調理自体が簡単だといえ、ショールームのようにきれいなのである。カウンタートップは模造大理石、その横にAGE社製の電気オーブンに4つ口電磁調理器。240ボルトなら火力も十分だし、電気代も安いはずであった。お母さんが何か言ったのをカリンが英語に直してくれる。「ちょっと、狭いでしょ。」それに答えて「すごく美しいですね。まるでドイツのインテリア雑誌シェーナー・ボーネンやツーハウスを見ているようです」とボクが言うと、カリンとお母さんが見合ってほほえんだ。ようやく気持ちがなごんできた。
翌朝、カリンがミュンスター市内を案内してくれる。市庁舎や郷土歴史館など主だった観光スポットを案内してくれる。カメラのフィルムが切れたのでドラッグストアによってもらった。さすがにドイツのアグファ社のフィルムがほとんどであった。イルフォードやコダックもある。しかし、フジやサクラは見当たらなかった。キャッシャーでフィルム代金を払う時にカリンがボクのニコマートを持ってくれようとしたが、その重さに目を丸くした。自転車の半分程くらいに感じる重さである。一眼レフを自転車旅行に持つことなどはある意味で滑稽であった。観光地で見かけるドイツ人の多くは、茶色の皮のケースに入れられたビューファインダーカメラを大事そうに使っていた。しかもそれらは決してコンタックスやライカといった一級品ではなかった。戦後日本のカメラメーカーはこれら二つのドイツ製レンジファインダーカメラをめざしてカメラ王国の基礎を築いてきていた。ニコンはコンタックスを、キヤノンはライカをそっくり真似たレンジ・ファインダー・カメラから出発し60年代に入ってようやく一眼レフによってドイツのカメラを追い抜いたと自負していたのである。
一般のドイツ人はカメラをはじめとするモノに対する執着心はないのだろうか。リースマンは人々が標準的に備える生活財の組み合わせをスタンダード・パッケージと呼んだが、日本ではテレビ、冷蔵庫、マイカーといった三種の神器をスタンダード・パッケージとする時代をすでに脱し、高度成長期の中でマイホームの夢を誰もが追っていた。マイホームはマイハウスではない。そこではホームとして家庭を包む箱が「あるかどうか」を問題にしているのであって、どんな包み方をするかという物理的、構造的、計画的なハウスではなかったのである。そんななかにあって日本のサラリーマンは一点豪華主義のカメラやライターにその夢を仮託していた。ドイツ人はどうか。カメラといったモノにとらわれている気配は感じ得なかった。どうも生活の中で追い求めるモノのプライオリティーが違うような気がした。ドイツでは住まうことから出発し、そこにこだわりその部品となる生活の構成要素は後からくる。それに対して、日本では小道具に思い入れはあっても、生活を包む空間にどれほど心を配ってきただろうか…。
カリンがレシートを渡してくれながら、明日はヴァッサー・シュロス(水の城)へ行きましょうと言った。
ヴァッサー・シュ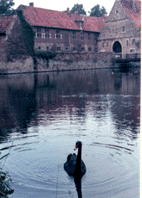 ロスは、中世後期に諸侯が建てた堀をもつ城である。この水の城がこの地方には点在しておりローカル・アイデンティティーを明確にしているようであった。
ロスは、中世後期に諸侯が建てた堀をもつ城である。この水の城がこの地方には点在しておりローカル・アイデンティティーを明確にしているようであった。
それからの数日はあっという間に過ぎ去って行った。州境に近い場所にあるサファリ・パーク、カリンとお父さんとのオランダのアムステルダムへのバス旅行などミュンスターでのボクの思い出作りをカリンたちは精一杯してくれた。ガービの家は駅から程近い集合アパートのなかにあった。彼女の家にはカリンが連れて行ってくれた。映画で見るのと同じように一階の入り口でブザーを押すと住人がドアホンで確認して解除ボタンを押す。そのブザーが鳴っている間にドアを開けて入る仕組になっているのだ。その手続きに妙に感動した。
ガービとお父さんのオットーさんの笑顔に迎えられて4LDKのアパートに足を踏み入れたボクは「オー」と声をあげた。全体が黄色を基調としたドイツの概念色にまとめられていたからであった。ガービが英語が苦手なため途中からむしろお父さんとの文通が主だったせいもあってオットーさんがいろいろと説明をしてくれた。客用の寝室がないからとカリンの家でボクを世話をすることになって申し訳ないと言われた。ガービのお父さんは証券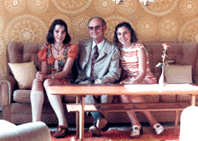 会社に勤めるサラリーマン。第二次大戦中は海軍予備役だったという。訓練を受けていたUボートはほとんどが爆撃でやられたそうだ。Uボートの色あせた小さなモノトーンの写真がオットー・ミヒャエルという署名入りで寝室の片隅にかけられていた。
会社に勤めるサラリーマン。第二次大戦中は海軍予備役だったという。訓練を受けていたUボートはほとんどが爆撃でやられたそうだ。Uボートの色あせた小さなモノトーンの写真がオットー・ミヒャエルという署名入りで寝室の片隅にかけられていた。
ボクのオヤジにしろ、ユングフラウで出会ったクレメント夫妻にしろ、ミヒャエル氏にしろ十代から二十代にかけての青春を戦争のなかで過ごした。彼らの思い出は必ず戦争という文脈において語られる。オヤジは砲兵中隊の少尉として上海で、クレメント氏はケンレーの空軍基地で、そしてミヒャエル氏はキールの海軍基地で終戦を迎えた。彼らは異なった経度で同じ戦争を共有していたのである。ボクが彼らの年代で思い出を語るときは、それがヨーロッパ自転車旅行という名の無垢なる放蕩に過ぎないことをUボートの写真は知らせようとするかのようであった。
オットーさんがサイクリングのアドバイスをしてくれた。彼も自転車でバイエルン地方を通ってノイシュバンシュタイン城まで行ったことがあると初めて語ってくれた。ヴュルツブルグからフュッセンへのびるロマンティッシュ・シュトラーサ(ロマンチック街道)は中世の面影を残しているからとガイドブックそのものの解説を延々としてくれた。次第にうなずくだけになったボクを見て奥さんがガービとカリンと三人で夕暮れのミュンスターの町を散歩したらと勧めてくれた。薄暮の中で靴音が反響する。地面が固く感じられた。石の文化の上を夏の時間がゆったりと過ぎゆこうとしていた。
翌朝、カリンの家のガレージで自転車を組み立てた。カレンダーは八月に変わっていた。ずっとカーステンがそばでその様子を見守る。朝食はハムと卵を炒めたものにライ麦パンが出た。ライ麦パンも3種類ほどあった。すでに家族との一体感のようなものを感じ始めていて朝食も珍しいものではなくなっていたが、何となく緊張感のようなものが食卓に漂っていた。朝食を済ませた後、ハーフパンツに着替えてカリンの家族に別れを告げた。自転車をかっこよく蹴り出そうとしたがリズムが合わずにハーフクリップに足をかけ損なった。近所の子どもたちも自転車でしばらく後を追ってきた。通りのはずれで振り返るとカリンがもう一度手を振ってくれた。
ヴュルツブルグまでは一気に走った。町を抜けると後は田舎道であった。行き交う車のドライバーがバックミラーでこちらを確認しているのがわかる。久しぶりに自転車を走らせたせいで身体が痛い。ヴュルツブルグに入るとすぐさまユースを探した。途中アメリカ軍の駐留している兵舎があった。通りを歩く淡いピンクのブラウスを着た女性に二人のアメリカ兵が視線を投げていた。その視線の延長上にボクの視線もあった。
明日からはロマンチック街道を走ることになる。人影もまばらなヴュルツブルグ城の坂道で自転車を停めてガソリンスタンドでもらったミシュランの区分地図を開いた。
第4回へ続く