ヨーロッパの青い空
Europe in Retrospective
その2

福本謹一
ユングフラウヨッホから帰った翌日、ベルンの隣町ルツェルンへ一人で行ってみた。そこはネバーランドのようなたたずまいを見せる白い街だった。風までが白く感じられる街。街の中を川が流れ、屋根付きの橋がかかる。川面に教会がゆれて石畳に響く靴音が心地よかった。ルツェルン駅からベルンに戻る列車の席の向かいにかわいらしい小さな女の子が乗ってきてちょこんとすわった。まだ6、7歳に思えた。窓の外で両親と妹らしい家 族が見送りに来ているようだった。おかあさんがこっちに目を向けて何か言い出したので、窓を開けてあげた。「ヴォー・ファールン・ジーン?」と聞かれたので、「Wo fahren Sie hin?」(どちらまで)のことかなと一旦活字に置き換えて弱々しく「ベルン」と答えたら、「この子はベルンの叔父の所に一週間遊びに行くので、ベルンまでよろしくね」と今度は英語で言われた。ベルンまでの短い時間、このテオドーラ・ウェンデルちゃんと片言のドイツ語で過ごすことになった。こんな小さな女の子でも一人で叔父さんの所へ行くのかと思うと、明日から一人で旅をするのに心細くなってなんかいられないと思った。
族が見送りに来ているようだった。おかあさんがこっちに目を向けて何か言い出したので、窓を開けてあげた。「ヴォー・ファールン・ジーン?」と聞かれたので、「Wo fahren Sie hin?」(どちらまで)のことかなと一旦活字に置き換えて弱々しく「ベルン」と答えたら、「この子はベルンの叔父の所に一週間遊びに行くので、ベルンまでよろしくね」と今度は英語で言われた。ベルンまでの短い時間、このテオドーラ・ウェンデルちゃんと片言のドイツ語で過ごすことになった。こんな小さな女の子でも一人で叔父さんの所へ行くのかと思うと、明日から一人で旅をするのに心細くなってなんかいられないと思った。
 バーゼルで念願のパウル・クレー美術館を訪れ、彼が14才で描いた石膏デッサンにうなされた。クレーのポエティックで思索的な表現の裏に実は冷厳な造形態度があったのである。スイスで出版されていた彼の「造形思考」を日本に帰国して読み直そうと思った。バーゼルからハイデルベルクへ向かう間、しばらく連結部に立っていたら、隣にいた白のヴェロアのTシャツにベージュのチノパンツ姿の学生っぽい女の子が「どこか空いた席を探してくる」とボクに英語で声をかけて中へ消えた。しばらくして戻ってきた彼女は、「女の子ばかりのコンパートメントが見つかったわよ。ラッキーでしょ」と人差し指をチョコチョコさせてボクを手招きした。自転車を連結部に置き去りにしたまま彼女についていった先のコンパートメントは確かに若い美人ばかりだった。コンパートメントという限られた空間の中で外国人の女性ばかりに囲まれたため、しばらくは身体を堅くして視線を合わせることもできなかった。フロントバッグを足下において、最初は横を向いて席を探してくれた彼女の灰色の眼をのぞき込むのがせいいっぱいだった。しばらくして国境を越えたのか、ドイツ鉄道を示すDBの記章をつけた車掌が来てパスポートと切符を形式的に改めた。このやりとりがあったせいで、ずいぶん気が楽になった。彼女はボクが思い描いていた「アメリカ人」のような雰囲気だったので、「ドイツ人?」とたずねると「パパはアメリカ人で、母が南バイエルンの出身」と、彼女はなぜかハーフ・アンド・ハーフのへしゃげたタバコを突き出しながら答えを返した。彼女は自分がハーフであることをそのタバコのネーミングに投影しているのかもしれないと感じた。父親はアメリカ軍の関係だという。年格好からして彼女が生まれたのはボクと同じ1952年頃のように思えた。彼女はドイツの戦後の復興期をどのような感性で見ていたのだろうか。通路越しの窓にはいつのまにかライン河がサイレント・ムービーのように流れていた。
バーゼルで念願のパウル・クレー美術館を訪れ、彼が14才で描いた石膏デッサンにうなされた。クレーのポエティックで思索的な表現の裏に実は冷厳な造形態度があったのである。スイスで出版されていた彼の「造形思考」を日本に帰国して読み直そうと思った。バーゼルからハイデルベルクへ向かう間、しばらく連結部に立っていたら、隣にいた白のヴェロアのTシャツにベージュのチノパンツ姿の学生っぽい女の子が「どこか空いた席を探してくる」とボクに英語で声をかけて中へ消えた。しばらくして戻ってきた彼女は、「女の子ばかりのコンパートメントが見つかったわよ。ラッキーでしょ」と人差し指をチョコチョコさせてボクを手招きした。自転車を連結部に置き去りにしたまま彼女についていった先のコンパートメントは確かに若い美人ばかりだった。コンパートメントという限られた空間の中で外国人の女性ばかりに囲まれたため、しばらくは身体を堅くして視線を合わせることもできなかった。フロントバッグを足下において、最初は横を向いて席を探してくれた彼女の灰色の眼をのぞき込むのがせいいっぱいだった。しばらくして国境を越えたのか、ドイツ鉄道を示すDBの記章をつけた車掌が来てパスポートと切符を形式的に改めた。このやりとりがあったせいで、ずいぶん気が楽になった。彼女はボクが思い描いていた「アメリカ人」のような雰囲気だったので、「ドイツ人?」とたずねると「パパはアメリカ人で、母が南バイエルンの出身」と、彼女はなぜかハーフ・アンド・ハーフのへしゃげたタバコを突き出しながら答えを返した。彼女は自分がハーフであることをそのタバコのネーミングに投影しているのかもしれないと感じた。父親はアメリカ軍の関係だという。年格好からして彼女が生まれたのはボクと同じ1952年頃のように思えた。彼女はドイツの戦後の復興期をどのような感性で見ていたのだろうか。通路越しの窓にはいつのまにかライン河がサイレント・ムービーのように流れていた。女の子ばかり4人だと思っていたら、驚いたことにその内の一人はフランス人の男の子だった。あまりにも端正で女性的ですらある顔立ちのためにハーフの女の子も見間違ったのであった。「残念だったわね」と彼女はボクの肩を小突いてひやかすと、「私はカールスルーエで降りるから楽しんで」という言葉を残してコンパートメントのドアを開けた。彼女の後ろ姿を見送りながら、ふと心細くなった。それをぬぐい去ろうと、隣の美顔のフランス人高校生と黒と白のチェック柄のミニスカートからすらりとした足を組んだ向かいの歯科医院の事務を勤めるという女性とハイデルベルクまで時折の沈黙を交えて会話をつないでいった。後の二人の若い女性は、無表情にボクたちの方へ視線を送るだけだった。
事務の彼女はドイツ語に英語の片言を交えて話すだけなので、高校生の男の子が彼女にはドイツ語でボクには英語でやりとりをする。聞いてみると彼はフランス語、ドイツ語、英語の他にイタリア語、スペイン語、オランダ語、デンマーク語を話せるという。ボクが東洋的な眼を思いっきり丸くしてみせると、高校でそれらの語学クラスがあると言った。「フランス人はフランス語しか話さないって聞いてるけど」と英語もろくに話せないのを恥ずかしく思いながら言うと、彼は「特に大人はそうかもしれないけど、旅行をするのにフランス語だけでできる訳じゃないし、若い連中はそれほどこだわってることはないと思う」と、向かいの事務員に視線を投げかけながら答えた。そのしぐさに急にコンパートメントが一つのヨーロッパのように思えてきた。その時窓の輪郭を切り裂くように真っ白い新型のトヨタ・セリカが横切り、その挑戦的なデザインの残像を残して消えた。
ハイデルベルク駅で彼女たち、いや彼らに別れを告げた。急にお腹が空いて、自転車を荷物預かりに預けて、駅を出たすぐの売店でホットドッグをザウアークラウトと一緒に買ってみた。ソーセージといっても種類がいっぱいあって選ぶのに躊躇したが、結局耳になじみのあるフランクフルターと書いてあるやつにした。実を言うとそれ以外のものがどういうものか想像がつかなかったのである。ソーセージは結構さっぱり味で口に合ったが、ザウアークラウトは胃が引き締まるように酸っぱかった。駅を行き交うドイツ人たちの様子をしばらく観察した後、まっすぐユースホステルへ向かう。ユースホステルに泊まるのはハイデルベルクが最初であったが、ユースホステル(ユーゲントヘアベルゲ)はドイツが発祥の地なので、料金も安い。素泊まりで一泊2マルク。200円程(当時の通貨レート)であった。食事を付けても5マルクくらいである。会員証には、泊まったホステルでそれぞれスタンプを押してもらうようになっているが、日本のユースのスタンプはきちんとその罫線枠に合うように細長い長方形になっている。ヨーロッパでは大きさもデザインもまちまちでユニークなものが多い。しかもスタンプの押し方もおうようである。民族性と言ってしまえばそれだけだが、ユースホステルの会員証にも世界が描かれ始めようとしていた。
翌朝ハイデルベルク城へ向かった。途中、ビスマルク・プラッツで野菜やソーセージの並ぶ市場が立っていた。緑と白のストライプのパラソルの下にそれこそじゃがいもや果物が所狭しと並べられている。能登半島をサイクリングして輪島の朝市に寄った場面を思い起こした。あまりの対比であった。輪島の朝市もある面で観光の一スポットであるには違いなかったが、そこにはもんぺ姿の農家のおばあさんがわずかばかりの野菜をござに並べて道ばたでじっと座って待つ「素朴な」光景がある。しかしビスマルク・プラッツのそれはあまりにもこぎれいなのだ。モノの並べ様はモンドリアンの絵画のようにミリ単位で配列されているかのようだ。売っているおばちゃんたちも刺繍の入ったエプロンをして口紅をさしている。これがドイツの「素朴さ」なのだろうか。いや、そうではない。この比較自体が間違っているのだ。ハイデルベルクは都会である。ましてやヨーロッパのプラッツ(広場)なるものは特別な意味をもっているに違いない。売られているモノを見て、「市場」という日本語に置き換えて考え始めたのがそもそも誤りなのだ。光景の類似性は必ずしも意味の等価構造を有してはいないのだ…朝の匂いはいろいろな思いを運んでいく。カメラをもつ人たちの流れを見つけて小走りに後を追った。ハイデルベルク城ももうすぐだ。
古城は想像したよりこじんまりしていた。城内をくまなく見ようという意志はなかった。巨大なワイン樽もアルト・ハイデルベルクの主人公のことも感興をそそるものではなかった。夏の陽射しにもかかわらず古城から見おろす街の赤茶けた屋根がどこか寒々しい。ふと一人旅であることを実感した。なだらかな山と薄灰色の平面がライン河の向こうにある。駆け足で城を後にした。
ハイデルベルクからボンへ向かう列車は結構混んでいたので、また連結部に立っていた。自転車を入れた輪行バッグがなくても、まだコンパートメントには一人で入る勇気がなかった。ハイデルベルクから家族連れが乗車してきた。英語を話し始めたのでつい隣にいた奥さんらしき人に声をかけた。フランクフルト駐留の米軍兵士の家族だった。夏期休暇に息子を訪ねてコネチカットから来たという。反対側のドアを背に若いソルジャーカットの青年の顔がある。視線が合ったが、彼は表情を変えなかった。奥さんとはフランクフルトまで時折言葉をかわしたが、ご主人と娘も会話に参加することはついになかった。
ボンでベートーベンの生家に行った。偉人の生家が全てそうであるように、ごくふつうの家であった。スイスの家もドイツの家も窓辺には赤い花が飾られている。ベートーベン・ハウスの緑の雨戸に赤い花のあざやかな対照がかえって興味を半減させていた。その記念館をそこそこにボン市内を歩き回った。独特の商店の看板がドイツへ来たことを再確認させる。看板は軒から突き出るように吊り下げられており、靴屋にはブーツを型どった鋳造レリーフ、肉屋には豚のマークというようにどの通りにも同じ位置にそれらが取り付けられていた。あまり派手な色使いのものはなく、窓辺の花と同じくこれらの看板も市条例で大きさや色や形が制限されているのかもしれなかった。
ユングフラウヨッホで写真のシャッターを押してあげたシュレイターさんの家を訪問すべく、もらった走り書きの住所を頼りにケルンに向かった。ケルン駅を降りた矢先に手荷物をもってやろうかという二人の子どもたちに迫られた。これが例の「ケルンのガキ」なのだと悟った。よく子どもが手荷物をもってやろうと旅行者に声をかけて注意を引きつけている間に別の子どもがカメラなどをひったくることがあるとあらかじめ注意をされていたので、周りを見渡しながら日本語で「あっちへ行け、このガキ!」と追い払った。
 シュレイターさんの住所は中央駅からそれほど遠くないと聞いていたので、歩いていくことにした。ライン河にかかるホーエンツォレルン橋を渡ってから通りすがりのみすぼらしい黒いスーツ姿の中年のおじさんに住所を見せて「ボ・イスト・ジー?」(これはどこですか)と聞いた。そのとたんに「ヤパン?」(日本人か?)と聞かれて、「ヤー、ヤー」と答えたのがよかったのか悪かったのか、その後立て続けにおじさんはドイツ語をまくしたて始めた。いろいろと親切に教えてくれているらしいのだが、ボクはちんぷんかんぷんだった。おじさんが一息ついたところでまた、「ボ・イスト・ジー?」と繰り返してしまった。するとおじさんはいきなりボクの手を引いて路面電車乗り場へ連れていって一緒に乗り込んだ。電車に乗っている間おじさんは何も言わなかったし、ボクもボーっとしたまま突っ起っていた。おじさんは3駅ほどいったところで車掌に知らせる紐を引くと、一緒に降りて通りの角を指さしながら「まっすぐ、右、左」と今度はゆっくり、言葉を切るように教えてくれたのである。わざわざ最寄りの駅までおじさんは連れてきてくれたのだ。ボクは、「ダンケ・シェン」を繰り返して、中央駅行きの電車が見えなくなるまでおじさんを見送った。
シュレイターさんの住所は中央駅からそれほど遠くないと聞いていたので、歩いていくことにした。ライン河にかかるホーエンツォレルン橋を渡ってから通りすがりのみすぼらしい黒いスーツ姿の中年のおじさんに住所を見せて「ボ・イスト・ジー?」(これはどこですか)と聞いた。そのとたんに「ヤパン?」(日本人か?)と聞かれて、「ヤー、ヤー」と答えたのがよかったのか悪かったのか、その後立て続けにおじさんはドイツ語をまくしたて始めた。いろいろと親切に教えてくれているらしいのだが、ボクはちんぷんかんぷんだった。おじさんが一息ついたところでまた、「ボ・イスト・ジー?」と繰り返してしまった。するとおじさんはいきなりボクの手を引いて路面電車乗り場へ連れていって一緒に乗り込んだ。電車に乗っている間おじさんは何も言わなかったし、ボクもボーっとしたまま突っ起っていた。おじさんは3駅ほどいったところで車掌に知らせる紐を引くと、一緒に降りて通りの角を指さしながら「まっすぐ、右、左」と今度はゆっくり、言葉を切るように教えてくれたのである。わざわざ最寄りの駅までおじさんは連れてきてくれたのだ。ボクは、「ダンケ・シェン」を繰り返して、中央駅行きの電車が見えなくなるまでおじさんを見送った。シュレイターさんの家は静かな住宅地の中にあった。周りには平屋建ての家が多かった。小さいけれどそれぞれ芝生の庭に囲まれ住み心地のよさそうな家ばかりであった。ドイツの住宅雑誌シェーナー・ボーネン(美しい住まい)に出てくるインテリアを想像しながら家番号を確かめてドアベルを押した。ドアは半開きになっていて奥の庭に面した窓の逆光の中から男の人が出てくるのが見えた。シュレイターさんは二日前に帰っているはずだったので、よかった、帰っていると気を強くした。しかし、彼はシュレイターさんではなかった。ボクと同じ年格好でやや太めの青年だった。長男のようであった。「シュレイターさんはいますか?」と彼に尋ねると、「父は弟と一緒に旅行に行っている」という応えが返ってきた。ボクは一瞬愕然となった。「スイスで会って、二日前に帰っているはずとお聞きしたんですが」ともぞもぞ言ったものの、彼は首を横に振るばかりであった。ボクはとぼとぼとケルンの中央駅まで歩いて引き返した。ホーエンツォレルン橋がえらく長く感じた。ユースホステルの食事も冷めていた。ボクは何かを期待しすぎていたことを反省した。
旅行費用の10万円を半分に分けてデュッセルドルフとパリの東京銀行支店にあらかじめ送金していた。(といっても、あつかましく勝手に郵便で送りつけていたので、受け取りの際に、担当の課長さんからくれぐれもこうした扱いはしていないのでと厳しく注意を受けた)ユースホステルを泊まり歩くのに持ち金はできるだけ少額にしておきたかったからである。パスポートや現金は女性のストッキングの片足を切って入れて腹巻きにしておいた。旅慣れた東京の叔母がそうするとよいとくれたものだった。デュッセルドルフは日本人の駐在員が多いせいか、日本料理店や寿司屋の看板が目立つ。お金をしまい込むと、日本語の看板を横目に駅に急いだ。ペンフレンドのガービとカリンに早く会いたかった。彼女たちは二人ともヴェストファーレン・ノルトライン州のミュンスターに
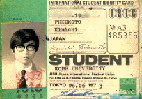 住む高校生であった。輪行袋をかついで昇る列車のステップがそれまでよりなぜか高く感じられた。
住む高校生であった。輪行袋をかついで昇る列車のステップがそれまでよりなぜか高く感じられた。ミュンスターに近づくにつれて明るい平屋建ての新興住宅地の向こう側にギルド的なたたずまいの建築物や小さな教会が見え始めた。広軌道のせいか列車の揺れは少なかったが、鼓動は次第に高まっていた。ミュンスターの駅を出ると乾いた陽光に思わず眼を細めた。そして輪行袋を引きずりながら駅前通りの向かいにあった公衆電話ボックスにボクは向かった…。
(続く)