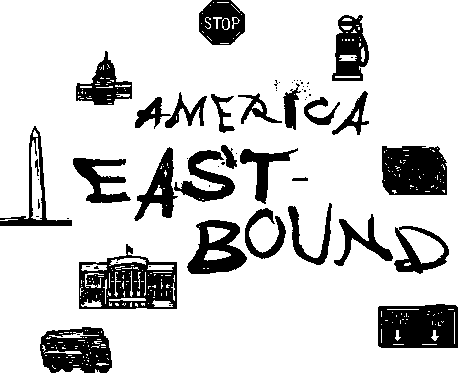
その4
福本謹一
ウォールデン・ポンドはボストンから16マイル程(約20キロ)西に行ったコンコードというところにある。実は、ナッシュビルに留学する際に持参した本が三册ある。一冊は鈴木大拙の「禅と日本文化」(岩波新書)、別の一冊はアメリカの画家アンドリュー・ワイエスの1973年の京都展カタログ、そしてもう一冊がヘンリー・デイヴィッド・ソローの「森の生活」(岩波文庫)であった。どれも学部時代に読んだ本でワイエスの画集以外それほどの思い入れはなかったが、どういうわけかこの三册になっていた。「森の生活」は原題が「ウォールデン」、すなわちウォールデン・ポンドのことである。この湖はソローが1845年の独立記念日から2年間、自然観察をしながら孤独な思索生活をした場所として知られる。そこでの生活を記した「森の生活」は、一般的にはソローの自然との協調や質素な生活をめざした考えを反映したアウトドアライフのバイブルとして知られていたが、その奥には彼の思想的背景がある。
1837年ハーバードを卒業した彼はエマソンと親交を深め、エマソンの薦めで文筆活動に入る。エマソンとの出会いは神秘主義と個人主義への関心をもたらすことになるが、彼はそうした思想を机上でもてあそぶことを嫌ってむしろ生活の中で実践することを信条とした。当時の人々が物質文明の弊害に冒され心底で絶望しながらそれに甘んじ黙々と生活する様を批判し、生活の簡素化を図り精神的な安定を求めるとともに明確な個人としての市民意識を抱くべきであるとする考えを「ウォールデン」において「実験」したのである。ウォールデンでの生活では当時まだ残っていた奴隷制に反対してコミュニティー税を納めることを拒否したが、その主張は1849年に「シビル・ディスオベイディエンス」(市民的不服従)として出版される。この著作はトルストイ、ガンジーといった平和主義者や米国の市民権運動のリーダー達に多大の影響を及ぼしたと言われ、ソローが生前2册しか著作を出版しなかったにもかかわらず名を残したのは「シビル・ディスオベイディエンス」にある社会的主張によるものであった。
ウォールデン・ポンドを訪れたいという理由は、こうした思想性ではなくアウトドアライフ的な興味からであったが、この旅行はソローへのそうした一面的な誤解に終止符を打つきっかけにもなった。ボストンからしばらくしてすぐにコンコードの表示が現れて小さなロータリーを過ぎればウォールデン・ポンドの表示が見える。その表示に従って左に折れれば湖まではそれこそすぐであった。「森の生活」からイメージされていたものとは明らかに違う様子であった。悪い予感がした。駐車場には2、30台の車がある。車を降りて「ウォールデン・ポンド」と「ソローの小屋」の表示の示す方向へ歩き出す。そのどちらもすぐに見つかったが、ボクは思わず目を疑った。どこに人里離れた「森の生活」があるのだろう。「ソローの小屋」はまさに何の変哲もない小屋であり、「ウォールデン・ポンド」はどこにでもあるような小さな湖であった。何か裏切られたような気持ちになった。その失望を誘ったものは「森の生活」という訳本の題名である。この本の題からはどう見ても町から遠く離れた森の奥を想像していまう。本の中では友人達が彼の小屋を訪れる箇所があるが、森の中までよく訪ねてくるなと不思議であった。しかし、その謎も一瞬にして解けた。湖への失望は訳本への怒りに変わった。ソローは決してアウトドアなんかを楽しむためにここに来ていたのではない。適当に町から離れていて、自然の鼓動が聞こえる場所でありながら、友人達とも気を紛らわすことのできる場所としてここを選んだだけだったに違いない。「何の変哲もない」理由はそこにあった。「森の生活」はあまりにも罪深いイメージを形成させていたのである。「ウォールデン」の本質は文明批判であり、一市民としての健全な生活と市民権問題だったのである。最初からそうした目で見ていれば、ウォールデン・ポンドのありふれた光景が自然のsuchness(あるがままの姿)として受け入れられたはずである。しかし、人間はわがままなものであり、「森の生活」という造られた自然の自己像を要求する。ウォールデン・ポンドへの「失望」は、どこかしら失恋に似ていた。
その時点ではソローを誤解したまま、ヴァーモントをめざして西へ進んだ。「ヴァーモントへようこそ」の標識を通り過ぎたのはウォールデン・ポンドを出て2時間程が過ぎた頃であった。ブラトルボロまであとわずかである。途中でジョイスに電話をかけてブラトルボロからの道順を確認した。地道に入ると葉タバコらしいものを栽培する農家が点在する。細い山道沿いにはところどころ木の幹にバケツが下がっていた。車を停めて見てみると、ブリキ管が幹に突き刺せられそこから樹液がバケツに垂れていた。これがメイプル・シロップなのかと合点した。メイプル・シロップはパンケーキには欠かせないし、ヴァーモントの代名詞にもなっていた。無造作なやり方だが、整然と垂直に伸びた木の幹に吊り下げられたバケツのさりげなさが美術作品のように輝いて見えた。
しばらく坂道を上るとジョイスのくれた絵地図にある小さな教会が森を背景に出現した。そこから左に折れて細い坂道を下ると小さな橋が見えるはずだ。手書きの絵地図は宝探しの地図のようにわくわくさせるものがあった。ボクはこの山道の中にウォールデン・ポンドを追い求めているような気がした。車が一台しか通れそうにない丸太橋の手前で車を停めると滝の音が聞こえてきた。滝を見ることはできないがその滝の下にジョイスの家があるはずだった。
湿り気を帯びた鬱蒼とした木々の間にロッジ風の家が現れた。
 すぐ下を川が流れている。滝の音はなかったが、この上手にあることは予想がついた。車のドアを閉める音を聞きつけてか、ジョイスと大型犬が迎えてくれた。ジョイスが両手を広げながらボクを抱きしめる。「これはクーライト。」人ぐらいはあろうかと思われるほど大きな犬であった。続いて、家の中から二人の男女が出てきた。「こちらは、娘のケルステン。そっちがジョン・チン。ロバートはブラトルボロまで行っているけどまだ帰ってこないの。」2人と握手を交わすと家の中に入った。ジョンはどこが非行少年なんだと思わすくらいまじめそうだった。「ジョンはあなたに連れて帰ってもらう約束だったけど、明日バスで帰ると言っているので先に帰すわ」とジョイスが言う。ジョンをワシントンまで送ることはなくなったが、後でジョイスと一緒にワシントンまで同行して家庭裁判所にだけは付き合うように頼まれた。
すぐ下を川が流れている。滝の音はなかったが、この上手にあることは予想がついた。車のドアを閉める音を聞きつけてか、ジョイスと大型犬が迎えてくれた。ジョイスが両手を広げながらボクを抱きしめる。「これはクーライト。」人ぐらいはあろうかと思われるほど大きな犬であった。続いて、家の中から二人の男女が出てきた。「こちらは、娘のケルステン。そっちがジョン・チン。ロバートはブラトルボロまで行っているけどまだ帰ってこないの。」2人と握手を交わすと家の中に入った。ジョンはどこが非行少年なんだと思わすくらいまじめそうだった。「ジョンはあなたに連れて帰ってもらう約束だったけど、明日バスで帰ると言っているので先に帰すわ」とジョイスが言う。ジョンをワシントンまで送ることはなくなったが、後でジョイスと一緒にワシントンまで同行して家庭裁判所にだけは付き合うように頼まれた。ログハウスは、ロバートが二年がかりで自分で建てたそうだ。まだ一部完成していなくて2階の仕事場は床板が途中までしか張られていなかった。ところどころに油絵や木彫が乱暴に置かれている。ジョイスが弁護口調で「ロバートはアーティストなのよ」と行った。しかし、どう見ても美術作品とは呼べそうもない代物ばかりだった。「敷地の中に滝があるから、ケルステン達と泳いできたら。疲れがとれるわよ」とジョイスに促されたが、思わず聞き返した。「滝が敷地の中にあるって?」「そこの川もうちの土地なの。冬には30センチくらいの氷が張って、それが春になれば解けて恐ろしいほどの音を立てて水が流れるの。人間は、自然を相手にしてはすごく弱々しい存在(vulnerable)だってことを実感するわ」とジョイスが遠くを見つめながらつぶやいた。その視線の先にまさにボクの思い描いていた「森の生活」があるような気がしてならなかった。ひょっとするとソローはここにいるのかもしれなかった。
ケルステンとジョン・チンに連れられて滝まで行った。滝
 は岩影に隠れて家からは見通せなかったが、30メートル程上手にあった。滝と行っても高さが5メートル、幅4メートル程の小さなものだったが、水流は結構あって水しぶきがあがる。滝壷は広くて、深さは2メートル程だと言う。いきなりジョン・チンが飛び込みを見せた。「庭先に滝か。」ボクは溜息をもらしながら水と戯れた。
は岩影に隠れて家からは見通せなかったが、30メートル程上手にあった。滝と行っても高さが5メートル、幅4メートル程の小さなものだったが、水流は結構あって水しぶきがあがる。滝壷は広くて、深さは2メートル程だと言う。いきなりジョン・チンが飛び込みを見せた。「庭先に滝か。」ボクは溜息をもらしながら水と戯れた。ケルステンはジョイスと前夫との間にできた一人娘で、公立の高校を1年で中退し、今は隣町にあるシュタイナー学校に通っていた。シュタイナー学校と言えば子安美知子の「ミュンヘンの小学生」で有名になったルドルフ・シュタイナーの開いた学校である。日本でも1977年から78年にかけて東京で高橋巌などのシュタイナー研究会がいくつか発足し、関心の高まりを見せはじめていた。彼は人間と世界の全体的関わりを「超感覚的認識」によって把握するための神秘学的思想を展開すると同時に、その意識覚醒の手法を独創的な形で示そうとしたが、それがシュタイナー学校で実践されたオイリュトミーなどであった。その学校が米国にもあることは知らなかったので、ぜひ訪ねてみたくなった。ケルステンにそのことをたずねると、すぐに教育内容を紹介してくれた。螺旋状の絵を描いたノートなどを見せて、「この形をゆっくり心の中で思い描きながら記していくの。人間の魂と世界との交感をめざすシンボルなの」と説明してくれた。オイリュトミーや有機栽培の作業など公立とは違ったカリキュラムで学習が進むのだと言う。ある程度知的な勉強も重視されているものの、課題意識を持って自主的な学習内容をノートに記述していくことが中心だということであった。ジョイスが「ニュー・ハンプシャー州のモンテッソリ・スクールの顧問もしているので、ついでにそこも案内するわ」と言ってくれた。それにしてもシュタイナー学校のような公立以外のオータナティヴ・スクールを見る機会ができそうなことで楽しみが増えた。東京教育大にいた時、東大の稲垣忠彦教授が教授学研究会の延長で美術教育研究会も主催しておられたので顔を出さしてもらっていたが、稲垣教授が在研報告を「アメリカ教育通信」という形で出版して間もない時期であった。その中で紹介されているオープンスクールやフリースクールなど学校の形態が問われている時期でもあり好機であった。「ジョンも明日帰るし、今晩丁度ケルステンが行っていた公立のブラトルボロ高校で高校生がミュージカルのオクラホマをやることになっているから中華料理でも食べてから見に行きましょう」とジョイスがメリットのタバコに火を付けながら言った。彼女が横を向きながら煙を吐き出す様子にボクはワイエスが描いた女性の姿を重ね合わせて、そのうち絵にしてみたいと思った。
しばらくするとロバートが帰ってきて、いきなり「オクラホマ」の曲を替え歌にして「ヴァーモント」を口ずさみながら「よく来た、よく来た」と訛のある英語で迎えてくれた。ジョイスに促されてすぐみんなで町に向かう。中華レストランはブラトルボロには一軒しかない。競争相手がいないわりに味は良かった。「オクラホマ」も高校生が演じるものとしては迫力があったし、舞台も衣装も凝っていた。小さな高校にしては会場は大きい。ジムナジウムだが、そうと感じさせないのはもともと多目的使用を考えているせいだろう。会場は大人から子どもまでぎっしりであった。コミュニティーでの公立高校の位置づけはずいぶん日本と差があるように感じられた。ヴァンダービルト大学でもフットボールの会場は5万人収容できる。人口50万の町にである。しかもプロの試合があるわけでもない。それでも人は来るのである。
ロバートが帰りの車でも「ヴァーモント」と口ずさんでみんなの笑いを誘う。暗い坂道で急に車のライトが消えて、ロバートが「ファイヤークラッカー」と叫んだ。あまりに突然のことだったので訳が分からなかったが、真っ暗闇の中でみんなが大声をあげてドアの外に飛び出していったのでこちらもつられて飛び出したが、呆然として道に転げたままであった。みんなは大笑いをしながら車にまた飛び乗った気配である。「キニーチ、ゲームなの。ゲーム」とジョイスが説明してくれる。どうもフルーツバスケットのようなものだったらしい。みんなはボクが呆気に取られて道に転がっていたのが余程おかしかったらしく、家に着くまで笑っていた。
次の朝ジョイスはジョンをニューハンプシャーのキーンのバス停まで送るついでにケルステンとボクを誘った。ジョンと別れてからキーン大学のジョイスの研究室へ立ち寄る。ジョイスは障害児教育の助教授をしていた。Ph.Dを取得するためにピーボディーに来ているが、同じ博士号でもEd.Dじゃつまらないしと言う。教授の道に進むにしても、研究費(グラント)を取ってくるにしても何かと有利だと言うことであった。
帰り道でモンテッソリ・スクールに寄って案内してくれた。モンテッソリの教具が整然と教室に配置されていた。ボタンかけ訓練用のものや、形態識別訓練用のものなど色も形もどこかあか抜けている。まるでヨーロッパの木製玩具のようにこぎれいなものばかりであった。確かによく考えられているし、フレーベルの恩物と似たところもある。モノとしての魅力はあったが、それらを前に操作する子どもの姿はそこから読みとれなかった。一対一対応的な操作教具が主なのでしかたないかもしれないが全体像をつかむには夏休みという時期が悪かった。
家に戻るとロバートの他に誰か来ている様子だった。ロバートが口元に笑みを浮かべて、「滝の所まで行って来いよ」と言う。言われるままに滝の方へ向かったボクは、思わず声を上げた。滝壷の下の所に全裸の女性が横たわっていたのである。あわてて戻ったボクをロバートがからかう。「いっしょにスキニー・ディッピングしてくればいいのに。」スキニー・ディッピングとは全裸で泳ぐことを言う。彼女は彼らの知り合いだったが、この近くではスキニー・ディップする場所がいくらもあるそうだ。好奇心が刺激されたが、彼らのスキニー・ディッピングはただ開放的なもの以外に何かありそうだった。
次の日、ニューヨークからケルステンのいとこで高校生のショーンがやってきた。ジョイスの弟の娘であった。ジョイスとロバートが「レトリート」の準備に行くと言う。「レトリート?退却するという意味だったかな?」と考え込みながら、ジョイスにたずねると、仲間で瞑想したりするのだと言う。ジョイスはそれ以上言葉を加えなかったので、2人の間には視線のやりとりしか残らなかった。ジョイス達の背中を送りながら、ボクは何か宗教的な意味あいを感じ取っていた。
ジョイスやロバートが「レトリートの準備」から帰って、夕方、みんなでケルステンの要望でブルック・シールズの「ブルーラグーン」を見に行くことになった。船が難破し、南海の島に生き残った2人の少年少女が成長して愛し合うというストーリーだが、ブルックが湖で身体を洗っている場面で初潮を向かえ、水が赤く染まるのに驚いて「アイム・ブリーディング、ブリーディング(血が出てるわ)」と叫ぶ様子に観客から一様に笑いが起こった。こちらは気恥ずかしい思いをしているのにケルステンやショーンも笑っていたので戸惑いを隠せないでいた。その夜家に戻ってケルステンやショーンと泳いだ時、月明かりの中でケルステンが「アイム・ブリーディング、ブリーディング」とふざけるのに一緒に笑ったものの彼らの笑いはどこに根ざしたものかまだわからなかった。
次の朝、ロバートとジョイスがブラトルボロに行くというので、一緒に行かないかと誘われた。ブラトルボロは人口2万程の小さな町だが、この辺りは決してメイプルシロップだけの場所ではなかった。NASA関連の宇宙産業や軍需産業を陰で支えるハイテクの中小企業が結構あるということであったが、外見からはどう見ても田舎にしか見えなかった。ジョイスのスウェーデン製の薄汚れたサーブは、窓ガラスを下ろすノブが壊れているせいでカタカタ音を立てて走っていた。「今度はホンダにするわ」とジョイスがウィンクしながら言った。しばらくして町のはずれにある小さな家に着いた。中からピアノの音が聞こえる。ロバートがピアノを弾く手マネをしながらノックをすることもなく玄関のドアを開ける。ずかずかと彼らが入って行くので、彼らの「ハロー」の後に続いて入った。
ピアノの音の在処には2人の人物がいた。弾いているのは若い東洋系の女性で二十歳頃に見えた。彼女は僕たちが入ってきたことに気づく様子もなく、指の先に神経を込めていた。もう一人は老人でジョイスとロバートを見ると相好をくずして抱きしめていた。ジョイスが「日本から来た友人のキニーチよ」と紹介すると彼は「コーヒーでもどう?」と気さくに応じてくれた。「キニーチ、誰か知ってる?ニューヨーク・フィルのゼルキン氏よ。」ボクはゼルキンのことはあまり知らなかったが、彼女の口調の中に「あの有名な」という修飾語を感じ取るのに時間はかからなかった。ボクはすぐさまおおげさな声をあげて彼女の意図に応えた。後から聞けばゼルキンは戦後チェコを去ってニューヨークに移住していた。ニューヨーク・フィルに迎えられたのは70年頃だそうだが、夏の間はニューヨークの喧噪を嫌ってここに住んでいた。演奏に一区切りがついたのか、赤いワンピース姿のピアニストが「ハーイ」と挨拶をした。彼女はフィリピンの天才ピアニストのセシル・リカドだということであったが、彼女も夏だけゼルキンにレッスンを受けるためにそこに滞在していた。どうしてジョイス達がゼルキンと知り合いなのかは、ロバートがチェコ人というよしみだけではなさそうであった。彼らの話の内容からゼルキンも「リトリート」仲間であることがわかってきた。ジョイス達の訪問はその打ち合わせが目的のようであった。
ゼルキンの家を去ってブラトルボロの町中でピザを食べてから、次に若いカップルの家に連れて行かれた。主人が出迎えたが、ビデオの接続に四苦八苦していたところらしく、ジョイスがいきなり「JVCって日本製のビデオでしょ。キニーチ、日本人は機械に詳しいんじゃない?」と振ってきた。「JVCってビクターのことだったかな…」とつぶやきながら裏に回ってみた。まだ、VHSカセット・ビデオが出始めて間もない頃で、カセットを入れるスロットが跳ね上げ式になっていた。アンテナ・ケーブルをつないでNBC、CBS、PBS、ABCのチャンネル設定をしてビデオが映るようにするまでそれほど時間はかからなかった。その間、ジョイスたちの会話から「レトリート」という言葉だけがボクの耳に届く。「レトリート」が何なのかますます好奇心がふくらんでくる。ビデオの接続が終わるとカップルから尊敬の眼差しを受け取ると、ひとしきりビデオ鑑賞会になった。夕方近くになって、ジョイスが「そう言えばフェノロサって言う人物は知っているの?昔日本にいたらしいのよ。彼女はその人の曾孫」とアメリカ人にしては小柄な奥さんのエヴリンに視線を送りながら言った。「えっ、フェノロサの?」というボクの驚きの声にエヴリンが「その壁の浮世絵は、曾祖父が残したものなの」となにげなく応えた。その時、ブラトルボロという田舎町が日本の美術史にプラグをつなげた。「フェノロサといえば岡倉天心と日本美術院を創設し…」 (5回へ続く)