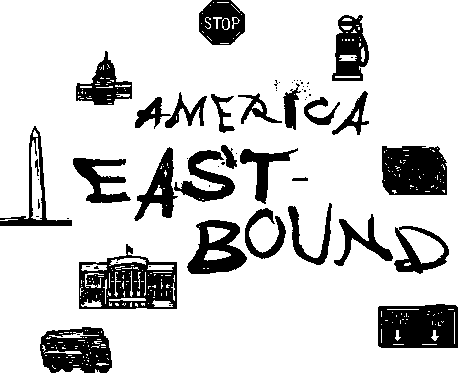
その3
福本謹一
ミニュウは、イランのテヘランで中堅石油会社を営むマジダメリ家の3人娘の長女で他のイランの裕福な家庭の子息と同じく、英国や米国の大学で高等教育を受けるべく留学していた。次女もカリフォルニア大学のサンタクルーズ校に在籍中であった。この時期、ホメイニの革命を察知したペルシャ絨毯商をはじめとして多くの人たちが国を後にしようとしていたが、マジダメリ家もその例に漏れず米国への移住の機会をうかがっていたのだ。
ミニュウの父と妹はフランクフルトを経由してルフトハンザでニューヨーク入りして、ワシントンDCのワシントン・ナショナル空港に午後12:40到着予定であった。ワシントン市街方面の標識は早くから見えていたが、インターステイト66号線はボク達をじらし続けてい
 た。腕時計の長針と短針が交わるその時になって、いきなりポトマック川が眼前に広がりその水平線の向こうにモニュメントが見えた。その水平線と垂直線の交わりにワシントンに来たという実感があった。その辺りにホワイトハウスやスミソニアンやモールがあり、ウォーターゲートがあるのだという期待感を携えながらダラス空港に急いだ。右手にアーリントン墓地やペンタゴンが見える。ポトマック川沿いのジョージ・ワシントン・メモリアル・パークウェイはそのままボクたちを空港に導いた。空港は市内から車で約10分程の極めて便利な位置にある。ワシントン・ナショナル空港はアメリカで最もアクセスのいい空港かもしれない。
た。腕時計の長針と短針が交わるその時になって、いきなりポトマック川が眼前に広がりその水平線の向こうにモニュメントが見えた。その水平線と垂直線の交わりにワシントンに来たという実感があった。その辺りにホワイトハウスやスミソニアンやモールがあり、ウォーターゲートがあるのだという期待感を携えながらダラス空港に急いだ。右手にアーリントン墓地やペンタゴンが見える。ポトマック川沿いのジョージ・ワシントン・メモリアル・パークウェイはそのままボクたちを空港に導いた。空港は市内から車で約10分程の極めて便利な位置にある。ワシントン・ナショナル空港はアメリカで最もアクセスのいい空港かもしれない。ワシントン・ナショナル空港(現ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港)の周回道路に入って一緒に出迎えようかとたずねたが、なぜかミニュウはここでいいからと送迎用のレーンに車を付けるよう指示した。車を停めるとミニュウはボクをきつくハグして今度はロスでとだけ言い残して小走りに国際線のターミナルへ急いだ。時計は12:30をややまわっていた。とにかく間にあった。バックミラーの中で彼女の姿がターミナルの回転ドアに消えていく間にふと疑問がわいた。どうしてミニュウは間に合わないかもしれないライドでわざわざワシントンへ行くことにしたのだろう。ロサンゼルスに直接飛べば済むことなのに。荷物も少なく、それになぜか家族と会わせることをためらうようなしぐさがあった。ワシントンで何か用事なのだろうか。そうした疑問も16時間という運転と2時間ばかりの睡眠でナッシュビルからたどり着いたのだというおおげさな感慨にいつしかすりかわっていった。チェッカーボードのようなDCの市内タクシーやマリオットやヒルトンといったホテル名を掲げたリムジンのナンバー・プレートの国会議事堂のマークを眺めているうちに、よそ者であることを意識した。それは「外人」ではなく「テネシアン」なのだという意識であった。ボクの中に東部とは違うという南部意識が芽生え始めていたような気がする。ボクのシェビー・ベガのプレートには「テネシー」と「ボランティア・ステート」という表記があった。
アメリカのナンバープレートは州によって色やデザインが異なり、州のニックネームが入っている。フロリダはサンシャイン・ステートという具合である。テネシーがボランティア・ステートというのは奉仕活動が盛んという意味ではなく、南北戦争以来、志願兵を多く出した土地柄によるものだ。南北戦争ではナッシュビル近辺の男たちは南軍、北軍へそれぞれの利害や義理で別れて志願したそうだ。それは、ミシシッピ川の支流になるカンバーランド川流域を境に南部諸州と綿花取引を河川流通で行っていた南側は南軍へ、タバコを主として東部と取引を行っていた北側の人々は北軍へついた。いずれにせよ、南北戦争以来、第一次世界大戦、第二次大戦、ベトナム戦争と多くの志願兵を排出したのがテネシーである。これがボランティア・ステートの由来であった。
テネシーは、不思議なアイデンティティーを持った州である。ボランティア・ステートという認識もそうだが、19世紀の初頭に東部の鉄道王であったピーボディーがこの土地に教育大学を設立したのも不思議といえば不思議である。そのせいかどうか分からないが、テネシーはことのほか教育熱心であった。いや、どこかお宅的な教育への熱情を歴史的にもっていた。ダーウィンの進化論がアメリカに伝わってくると、理科教育において進化論を教えるのはクリスチャンの教義に反すると、高校の教師が授業をボイコットし、裁判ざたになってイギリスからわざわざ進化論者達がその説明に乗り込む国際的なスキャンダルに発展した。今世紀ではケネディの時代、スプートニクショックを反映して理数科教育の立ち遅れの認識がなされ、英才教育、いわゆるヘッドスタート教育が唱えられたが、それを真っ先に取り入れたのもテネシーである。そのくせ、小学生のアチーヴメントテストの成績は全米50州の47位(1979年当時)である。教育への関心が高いことと実績とはなぜか結びつかないでいた。
ワシントンへ着いたら、ジョイスの兄の家に連絡するようになっていたが、夕方まで辺りを探索することにした。ダラスの空港から中心部へ向かう途中でペンタゴンへ寄った。ツアーにでも参加しようかと思ったが広大な駐車場をうろうろするうちに急に眠気に襲われいったん車を停めた。気がついたときには3時を過ぎていた。ペンタゴンはあきらめてアーリントン橋を渡ってリンカーン記念堂のある対岸へ渡ることにした。通りすがりの海軍の白い制服将校らしい人にわざとらしくモールへの道筋を聞いた。橋を渡って、ともかくおおまかなワシントンのマップを頭に入れるために車で流した。モニュメントは混んでなさそうだったので、パーキングメーターのある位置に車を停めて登ってみた。おのぼりさんは高いところに登るのが一番である。リンカーン記念堂と国会議事堂を挟んでモールと呼ばれる芝生の公園があり、その脇をスミソニアン博物館、航空博物館、ナショナル・ギャラリーなどの観光スポットがかためる。リンカーンとジェファソンはさしずめ仁王像といったところか。その360度の光景を頭に入れた後、議事堂からペンシルベニア通りを通ってホワイトハウスに向かった。道が空いていたこともあってホワイトハウス前で車を一時停車して記念写真を撮った。モールの周辺は方形区画で一方通行にさえ慣れれば、簡単だったが、くせ者はマサチューセッツとペンシルベニア通りである。これらの道はその方形を斜めに横切るためにうっかりするとかなり遠くに離れてしまう。おかげで東京で言えば原宿のようなジョージタウンに偶然出てしまった。しかし町を歩く時間的余裕もなかったので、モールに引き返して宇宙博物館の裏手でランディに電話をした。
低い声の奥さんの指示に従ってダウンタウンを後にコネチカット・アベニュウを北へ進む。家までは15分程であった。ワシントンは黒人が70パーセントを占め、住宅の人種構成でドーナツ化現象の進むところである。ランディたちはちょうど黒人と白人の住み分けの境界領域に住んでいた。ランディと奥さんはともに視覚に障害がある。ランディは3年前まで国務省に勤め、ウォレス国務長官時代には英国大使館の情報室部長として派遣されていた。眼病のため依願退職したとのことであった。どのような眼病だったのか、英語のヴォキャブラリーを超えていたためにわからなかったが、視力がかなり落ちているように見受けられた。やめる前は中東の情報分析が主な仕事だったそうで、イラン情勢については、国務省とCIAで意見が対立していたという。今はソビエトの南部での動きが気にかかるということであったが、その辺
 の事情にはうとかったのでただうなずくしかなかった。奥さんが全盲であることはすぐ見て取れたが、夕食を用意する所作はそのことを感じさせないほどであった。しかし、それがかえって痛々しさを感じさせた。あえてそのことを口にすると、彼女は「冷蔵庫でも何でもブレイズがついていて慣れれば支障がないわ」と表情を変えずに答えた。見れば確かにオーブンや冷蔵庫のスイッチ類すべてに点字の浮き出しがついていた。家電メーカーが視覚障害者用にオプションとして用意しているものだそうだ。公共的な施設に義務づけられた身体障害者用のスロープを始め、社会的弱者、マイノリティーへの配慮が至る所で見られた。理念よりも方法を優先させるアメリカ社会の一端を冷蔵庫のブレイズに見たような気がした。
の事情にはうとかったのでただうなずくしかなかった。奥さんが全盲であることはすぐ見て取れたが、夕食を用意する所作はそのことを感じさせないほどであった。しかし、それがかえって痛々しさを感じさせた。あえてそのことを口にすると、彼女は「冷蔵庫でも何でもブレイズがついていて慣れれば支障がないわ」と表情を変えずに答えた。見れば確かにオーブンや冷蔵庫のスイッチ類すべてに点字の浮き出しがついていた。家電メーカーが視覚障害者用にオプションとして用意しているものだそうだ。公共的な施設に義務づけられた身体障害者用のスロープを始め、社会的弱者、マイノリティーへの配慮が至る所で見られた。理念よりも方法を優先させるアメリカ社会の一端を冷蔵庫のブレイズに見たような気がした。彼女は実は、中国人の前夫をもち彼との間にジョンという息子がいた。ジョンはアーリントンの公立高校に通っていたが、非行のために停学処分になっていた。そのため一年間ジョイスのところで面倒を見てもらうことにしようと考えており今度家庭裁判所でその承認を受ける予定とのことであった。「ジョンは先週からジョイスのところへ行っているので、帰りがけに一緒に連れて帰って欲しい」と頼まれた。ランディの所へはその晩泊めてもらって次の日には発つことにした。

ワシントンからニューヨーク、ボストンを経由してジョイスの住むヴァーモントのブラトルボロまで車で直行すれば14時間から15時間の距離である。しかしどうせ1人旅なので友達の実家にも寄りながら行くことにした。ワシントンから北上すると、ボルチモア、フィラデルフィア、といったアメリカ建国に由緒のある場所を次々と通ることになる。美術に関してもそれぞれ大型の美術館があり楽しみには事欠かない。
ニューヨークへはニュージャージー・ターンパイクという道をとり、途中でマンハッタン島の方へ曲がるのを忘れてワシントン橋のある所まで行きすぎてしまった。そのため、9Aという出口で下りてマンハッタンに入った所はえらく黒人の多い場所だった。そこはハーレムのど真ん中だったのである。別に何をされるというわけでもないだろうが、思わずドアロックをしてしまった。信号機が赤に変わって一時停車を余儀なくされる間黒人の子どもたちが車に迫ってくる。最初は何も分からず緊張が走ったが、窓を拭きに来て金をせびるのである。しかたなく25セントを2、3枚渡して青に変わるのを待つが、セントラルパークに出るまでがすごく長く感じられた。いつものように2時間ほどかけてマンハッタンを北から南へとにかく走り回った。土地勘を得るためにはこうした探索が欠かせない。そしてイーストリバーの中埠頭にヘリポートが
 あったので、ヘリに乗って観光することにした。自由の女神とマンハッタン南側を巡るヘリツアー35ドルというやつを選んだ。スウェーデン人の母娘が一緒に乗り合わせた。高校生の娘はKANSAIと大きくプリントされたまるで法被のような上着を着ていた。日本のファッションデザイナーも結構認知されているのだと思いつつヘリに乗り込んだ。
あったので、ヘリに乗って観光することにした。自由の女神とマンハッタン南側を巡るヘリツアー35ドルというやつを選んだ。スウェーデン人の母娘が一緒に乗り合わせた。高校生の娘はKANSAIと大きくプリントされたまるで法被のような上着を着ていた。日本のファッションデザイナーも結構認知されているのだと思いつつヘリに乗り込んだ。ヘリはイーストリバーを一気に南下して自由の女神に飛ぶ。小型のヘリは普通の航空機と違って曲がるときが急なのと足下からも景色が見えるのでちょっと恐いが、病みつきになりそうであった。雲一つない晴天をバックに自由の女神がこちらを見据える。風が強いせいかヘリの揺れは大きかったが、星条旗が真横にたなびき、写真のショットには絶好であった。この写真は後に日本の高校の英語の副読本の表紙に使われることになった。日本人の設計になる双子の世界貿易センタービルからエンパイアステイトビルまではまるでマンハッタン地図会社の製作した立体化された地図を見るようであった。整然と区画された道が林立するビルの谷間に奥行きを与えている。15分の飛行予定が18分ほどかかった。サービスしてくれたのかどうかは分からないが、ともかく空の旅を堪能した。
夜は一泊20ドルのYMCAに泊まって二日かけてメトロポリタン美術館、近代美術館、自然史博物館、ソーホー、5番街、タイムズスクウェアといった観光スポットをおさえた。次の日、夏休みで帰省していたジョンのロングアイランドにある家を訪ねた。彼とはピーボディとヴァンダービルトの乗り入れ授業で仲良くなっていた。ジョンの父親はニューヨーク市警のアンタイ・テロリズム・スクアッドすなわちテロ対策騎馬警官である。ちょうど非番の日だったので会うことができたが、「聞こえはいいが、月給が安くて」とボクにくっ
 たくなく話してくれた。聞けばかなりな安月給で、日本の公務員にも満たない額である。これでは映画の中で描かれるニューヨークの警官が賄賂を受け取るのもまんざらフィクションでもなさそうであった。確かにジョンの家は中流の中という感じで決して裕福な感じはない。しかし、奨学金をもらってないはずのジョンがなぜ南部では授業料が最も高いという意味で皮肉を込めて「南部のハーバード」と呼ばれる大学を選んだのか、そして南部でなければならないのか疑問に思った。ジョンの家庭にとっては、彼をヴァンダービルトにやることはかなりな負担であるはずであった。元々ピーボディにいたボクは入学時の授業料がそのまま適用されていたのでヴァンダービルトのほぼ半額で済んだし、奨学金も幾ばくかあった。
たくなく話してくれた。聞けばかなりな安月給で、日本の公務員にも満たない額である。これでは映画の中で描かれるニューヨークの警官が賄賂を受け取るのもまんざらフィクションでもなさそうであった。確かにジョンの家は中流の中という感じで決して裕福な感じはない。しかし、奨学金をもらってないはずのジョンがなぜ南部では授業料が最も高いという意味で皮肉を込めて「南部のハーバード」と呼ばれる大学を選んだのか、そして南部でなければならないのか疑問に思った。ジョンの家庭にとっては、彼をヴァンダービルトにやることはかなりな負担であるはずであった。元々ピーボディにいたボクは入学時の授業料がそのまま適用されていたのでヴァンダービルトのほぼ半額で済んだし、奨学金も幾ばくかあった。翌日ジョンに別れを告げてボストンまで5時間ほどかけて行った。ワシントンに来るまでは気がつかなかったが東部には有料道路がけっこう多い。もっとも、せいぜい25セントとか50セントなので日本の有料道路とは違うが、それでもフリーウェイが当たり前のアメリカでは25セントでもわずらわしい気がする。ただおもしろいのは無人の集配ブースが多いことである。おつりの必要な場合だけおじさんのいる、いやおばさんもいるブースに入る必要があるが、そうでなければ大きな篭がせりだしたレーンに入ってコインを投げ込めば通れる。ただし、投げ込まずに通り抜けようとすれば鉄製のゲートがすぐさま閉まって御用となるようにできている。しかし、日本でいうバイパスにあたるパークウェイやターンパイクはたとえ有料の所であっても通る価値はある。思わぬ光景を期待するとすればこうしたパークウェイか超ローカルな
 道を行くにかぎる。
道を行くにかぎる。知り合いのジェニファーが「ボストンを通って行くのなら実家に泊って」と言われていたので、気軽に電話をしてみることにした。「話は聞いていたから、すぐこっちに来い」というお母さんの言葉に甘えて、お宅へ直行した。ジェニファーの父親はスコットランド出身の獣医をしており、なかなか裕福そうであった。娘のジェニファーはナッシュビルでダンスの講師をしており、ジョイスと同じく「審美教育ワークショップ」で知り合った。彼女は、テネシーの身体障害者のためのオリンピックでケネディー大統領の姉ユーニス・ケネディが発起人となったスペシャル・オリンピックのテネシー州大会のコーディネイターの一人であった。その後彼女の取り次ぎでテネシー州大会の聖火台のデザインをやらせてもらったり、美術ワークショップのコーディネイトをさせてもらった。
彼女の実家での思い出はなぜか食に関するものばかりであった。その晩、ジェニファーの両親は市内のシーフード・レストランへ案内してくれて、生牡蛎をこ
s.jpg) れでもかと言うほど食べさせてもらった。ナッシュビルにもシーフードの店は多いが、キャットフィッシュを除いてはメキシコ湾から運ばれてくるものがほとんどである。その点、ボストンは港町であり、漁港でもある。何しろ魚は新鮮だ。翌朝はコーンフレークにブルーベリーと苺を混ぜたシンプルなものだったが、アメリカでは珍しくそのフルーツが新鮮であった。スーパーに並ぶ大抵の果物がロウでてかてかに光っているのが当たり前なのに。味覚は記憶を増幅する。
れでもかと言うほど食べさせてもらった。ナッシュビルにもシーフードの店は多いが、キャットフィッシュを除いてはメキシコ湾から運ばれてくるものがほとんどである。その点、ボストンは港町であり、漁港でもある。何しろ魚は新鮮だ。翌朝はコーンフレークにブルーベリーと苺を混ぜたシンプルなものだったが、アメリカでは珍しくそのフルーツが新鮮であった。スーパーに並ぶ大抵の果物がロウでてかてかに光っているのが当たり前なのに。味覚は記憶を増幅する。ワシントンのランディーの家に泊まって以来、ジョイスには連絡しないままになっていた。そろそろヴァーモントをめざさなくてはならなかった。ボストンからブラトルボロまで約5時間。ただ、一カ所だけ寄り道したい場所があった。ヘンリー・デイヴィッド・ソローのウォールデン・ポンドである。
続く