ヤァ、ヤァ、ヤァ、傍観者がやってきた!
福本謹一
1993年8月18日、購入したフォー・バイ・セヴンの絵をやっとの思いで宿舎に運び入れた。どうしても階段を通り抜けず、ロープを買いに走った後、裏のベランダから吊り上げた。前日カナダから帰国したばかりで、時差ぼけ頭だったところへ、階段を曲がりきれないという計算外のことがあって、絵画購入の感激も少々薄れてしまった。フォー・バイ・セヴンは伊達にカタカナではなかったのである。日本の住空間は、円高差益還元されることは永遠にないだろうという気がした。
大学院入試の試験監督を免れた日の午前中の出来事としては、これだけのことであるが、この絵は、そのサイズ以上の意味があった。
5月14日から2週間、郷里岡山のヒロ・チカシゲ・ギャラリーで、高校の同級であった山口隆子が帰国して日本で始めて個展をするというので、彼女の実家へ電話してみたところ、15日にミニ同窓会をやることになっていて、「なんで連絡いっとらんのじゃろうかなあ。ええからあんたも来られえ」というこてこてのおかやま弁に誘われてギャラリーの閉まる1時間前にのぞきに行った。その時ギャラリーには、受付嬢以外誰もおらず、ひとわたり、絵をじっくり見ることができた。実は、この日、ロサンゼルスで活躍する同窓のタカコ・ヤマグチを応援する意味で、気に入った小品でもあれば、14、5万円までなら買ってみてもいいと決めていた。しかし、並べられた10点ほどの作品のスタイルは、想像していたものとは異なって、どこかしら東洋的で、ガンダーラ的でさえあった。しかも小品は最低でも、63万という表示がされていた。これではとても付き合いきれないということで、奥の応接室で待たせてもらっていた。そのテーブルにあった米国の美術雑誌をいくつかめくるうちに、それらがポストイットをはさんでいることに気づき、彼女の作品を載せたものであることがわかった。そうこうするうちに、20年前に辿ればそれらしい顔もそろい始め、懐かしい会話が始まった。山口隆子はまだであった。何人か集まって、会話が途切れたのを機に、雑誌をまた手に取った。Art Forumの1988年の8月号である。それとなくめくるうちに、眼を奪われた。そこに、タカコ・ヤマグチの作品を載せたロサンゼルスのジャン・バウム・ギャラリーの1ページ広告があった。その絵は、右端に、ボッティチェリを思わせる女性の立ち姿があり、画面の残り4分の3は、風景になっており、雲海、山脈、森、円柱を連ねた構造物が配されている。"enchanting"という形容がぴったりのもので、まさに魔法をかけられたようにその絵に魅了された。この絵は?と戻ってきたギャラリー主の近重氏に聞くか聞かないうちに、山口隆子が来たらしく、ギャラリーは一度に賑やかになった。「その絵は、セキュリティー・パシフィックに入っているらしいが、同じシリーズのものでもう少し小さいものならうちで預かってます・・・」という近重氏の言葉は、「そろそろ行きましょうか」というレストランへの移動を促す合図と重なって、その場限りのものとなるはずであった。
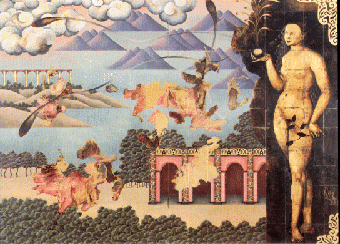 山口隆子は、高校時代は、「できる奴」の一団にいて、担任からは東大の文学部を進められていた。型にはまることを嫌ったのか結局、国際基督教大学(ICU)に進む。その後、同窓会名簿には、「カリフォルニア在住」という記載しかなく、それは居所不明と同じ響きしか持たなかった。しかし、現実には、全く別のコンテクストでしっかりとしたストーリーを展開させていたのである。
山口隆子は、高校時代は、「できる奴」の一団にいて、担任からは東大の文学部を進められていた。型にはまることを嫌ったのか結局、国際基督教大学(ICU)に進む。その後、同窓会名簿には、「カリフォルニア在住」という記載しかなく、それは居所不明と同じ響きしか持たなかった。しかし、現実には、全く別のコンテクストでしっかりとしたストーリーを展開させていたのである。
ICUに2年ほど在籍した後、授業に嫌気がさした彼女は、奨学金を出してくれるというメイン州のベイツ・カレッジに転校した。マスキー上院議員を生んだ大学である。この小さなカレッジで受けた美術の授業を転換点に彼女は作家への道を歩み始める。1年後、ニューヨークのデッサン展に出品し、2年生で最高の成績を収めたという。ハーバード大学のフォッグ美術館へ通い、もぐりの学生として講義を盗み聞きしたこともあるという。フォッグ美術館では、ドガのオリジナルのデッザンを貸してくれ、自分の手元において勉強することができたそうだ。76年にはカリフォルニア大学サンタ・バーバラ校の美術学科の修士課程に授業料免除生として入学。修了後、ロサンジェルスで家賃月207ドルのビルの1フロアを借りて作家活動に入った。80年にニューヨークのキャスリン・マーケル・ファイン・アーツ・ギャラリーで個展を初めて開く。作品8点は、2日目夕方のレセプションを開く前に全部売り切れになった。1点1600ドル。50%が画商の取り分であったが、「絵で食っていける」ことになった。その後は、サンフランシスコ(グレイプステイク・ギャラリー)をはじめとして各地で個展を開いていく。1983年以降は、ロサンジェルスのジャン・バウム・ギャラリーがホスト・ギャラリーとなって、活動を展開しているのである。最近では、ロサンジェルス、ニューヨーク、メキシコ・シティー、ベルリンと活動の拠点を広げつつある。
6月の末になって、ヒロ・チカシゲ・ギャラリーから、Art Forumの1988年の8月号にあったタカコ・ヤマグチの作品のコピーが送られてきた。私は、この絵が欲しくなってきた。既にサンフランシスコのセキュリティー・パシフィック・ナショナル銀行が4万7千ドルで購入したものであることを聞かされていたにもかかわらずである。そのサイズは、シックス・バイ・エイトで縦180センチ、横240センチほどにもなる大作である。そのコピーを調べるうちに、タカコ・ヤマグチがモダニズムとナショナル・アイデンティティーとの間を行き来する旅人であることがうかがい知れた。
タカコ・ヤマグチの作風というか、スタイルについては、岡山での個展を訪れるまで、全く知らなかったわけだが、87年に制作され、Art Forumに載った「イノセント・バイスタンダーNO.1」(無垢なる傍観者)と題された大作は、作家として出発した時点から現在に折り返すちょうど中間点にあたるものとして、彼女の芸術を理解する上での鍵となるものであった。
ルネッサンス的な人物表現によって、全体的には、西欧的な香を漂わせているものの、ランドスケープは、実景や3次元的な空間がねらわれているというよりも景趣を主眼としている。大和絵的な手法で描写されたそれが、金箔によって気品を与えられているところは、金碧障屏画の伝統を汲むように感じられた。濃絵(だみえ)は、濃彩画のことであり、金箔押しの画面に濃彩、とりわけ丹(朱)と碧(青)を基調とする。色調からしても、「イノセント・バイスタンダー」は、柔らかいピンクがかったオレンジとライトブルーの遠景を金箔の上に乗せている点で、金碧画の延長であるような錯覚を覚えさせる。それにもかかわらず、私のうちにあるエキゾチシズムをくすぐるものは、ルネッサンス的な女性像への憧れであり、宗教画的な趣であったろう。
しばらくして、チカシゲ・ギャラリーから、手元に預かっているという「イノセント・バイスタンダーNO.4」の明らかに露出不足の写真が届く。これには、ややがっかりしたものがあった。左端に女性像が移り、「NO.1」とは対称をなす構図である。同じシリーズのうちでありながら、印象は極めて異種のものであった。特に、女性像の顔は、西欧的な色彩を失い、東洋的なそれへと変化していた。この時点で、その写真は、カタログとしての使命を終えていた。それから2週間ほどして、近重氏から、現物を見てもらいたいという画商としての申し出があり、社まで出向くという。「これは、困ったな。でも買わないぞ」という意志を持ちつつも、「イノセント・バイスタンダーNO.1」の持つ質感を知るうえでぜひ見てみたいという衝動に駆られた。
近重氏が、研究室に絵を持ち込んだのは、6月25日の午後である。そこで意外な発見をする。「イノセント・バイスタンダーNO.4」は、厚手の洋紙にジェッソを施し、そのうえに金箔押しをした後、着彩された油彩画であった。それを丁寧に巻いた状態で彼は運んできた。ゆっくりと開かれてゆく絵の端から、金箔の鈍い光が明確な意志をもって訴えかけてくるようであった。それは、ずしんと重かった。露光不足の写真が計算されたものであったかのように、今になって、本物の凄みを感じさせた。「じゃあ、いただきます」という言葉が口をついて出た。後に引けなくなった。
その後、裏打ちをして、画面保護のためにアクリル板を入れた額装を2か月待つ間、自問していたことがある。それは、この絵が「イノセント・バイスタンダーNO.1」のサブスティテュートかどうかということであった。NO.1を所有できない代わりにその代替物として我慢しているに過ぎないのではないかという点である。これには一応の答えを出し得た。「イノセント・バイスタンダーNO.1」に私が見ていたものは、ある種の完璧さであり、身動きのできないほどの様式上の完成度の高さであった。すべてのモチーフが響き合うようにブレンドされていた。それに対してNO.4を眼にして抱いたある種の困惑、もしくは精神の揺らぎは、モチーフのミスマッチ感覚に起因する。端にたたずむ女性像は、ボッティチェリというよりも、クラナハやデューラーが描くエヴァのようにどこか歪な姿態を見せて北方ルネッサンス的な叙情をたたえる。しかし、顔は東方を意識させるものであり、ランド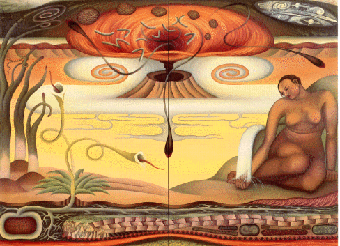 スケープのなかに存在するファサードは、どこかしらペルシャ的である。それらの間を精子が飛び交い、胎内で飛散したようなデカルコマニー状の不定形が散らばる。しかし、そこに認められるわずかな様式の変容こそは、次なる表現へ向けてタカコ・ヤマグチが変態をとげつつある予感であったのだ。脱皮した抜け殻がNO.1であり、追及する生の姿をしっかりと受け渡した証拠だったのである。NO.4にはむしろ、人間の生命の根源をなまめかしくも尊厳をもって照らそうという輝きが秘められていた。
スケープのなかに存在するファサードは、どこかしらペルシャ的である。それらの間を精子が飛び交い、胎内で飛散したようなデカルコマニー状の不定形が散らばる。しかし、そこに認められるわずかな様式の変容こそは、次なる表現へ向けてタカコ・ヤマグチが変態をとげつつある予感であったのだ。脱皮した抜け殻がNO.1であり、追及する生の姿をしっかりと受け渡した証拠だったのである。NO.4にはむしろ、人間の生命の根源をなまめかしくも尊厳をもって照らそうという輝きが秘められていた。
このことを確認することは容易である。90年代に入ってからの作品では、屏風絵的な景観は影をひそめ、劇場的な空間が広がる。根や化石や鉱物やこみ上げる溶岩流などであふれる地下世界があらわになり、地下領域の上に、怪しくうごめく植物やうねる水路が画面を横切る。火山は爆発し地中の核と天体が引き寄せられた天空を軽妙につないでいる。精子や染色体の舞い散るなかで、セクシュアリティーがダーウィン的な語り口で謙虚に展開する。生命体のミクロとマクロとの交互作用を媒介するように女性像は、エロチシズムよりも生命への畏敬を伝える。そのためにも、ミューズ的であるよりもブッダ的な表情を必要としたに違いない。「ラディアル・シンメトリー」や「無題」に感じられるユートピアとも彼岸ともとれる心地よい緊張関係は、「イノセント・バイスタンダーNO.4」の中に予知されていたのである。 タカコ・ヤマグチの中には、ナショナリズムを感じることはできるが、それは決してアメリカでのポピュラリティーを意識したものではないし、ましてや日本の美術界を見据えたものでもない。彼女自身「無垢なる傍観者」として、一般に予期される枠組みを超えてステイン・アライヴしているのである。 いずれにせよ、こうしてチェイス・マンハッタン銀行(ニューヨーク)、セキュリティー・パシフィック・ナショナル銀行(ロサンジェルス)などの法人に始まるタカコ・ヤマグチ作品のコレクターの最後尾に私の名前が加えられ、「イノセント・バイスタンダーNO.4」は、リビングの壁面を占有することになった。そして、toward a transformative selfへの励ましを確かなメッセージとして送り続けてくれている。 ようやく、肩の力を抜いて、「友達の絵を買った」と言えそうである。
