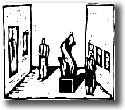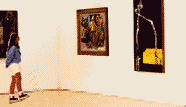
学校教育における鑑賞学習と美術館の連携を考える
兵庫教育大学芸術系教育講座 福本謹一
「ミイラになるのには、いくら(金額)ぐらいかかったのですか」。これは、児童文学作家カニグズバーグの『クローディアの秘密』(岩波少年文庫)の中で、家出をしたクローディアがメトロポリタン美術館のエジプト美術コーナーでギャラリーガイドの話を聞く小学生の一団に混じって質問をする場面である。
この本が出版されたのが1967年。既にアメリカの美術館が公立学校に対する教育普及活動を日常的に行っていたことが描写されている。それから約30年を経て日本の図画工作科、美術科においても鑑賞教育がようやく市民権を得ようとしている中で学校と美術館とのつながりを考えた教育実践も見られるようになってきた。
■学校における鑑賞教育への関心の高まり
小学校の学習指導要領図画工作科編の改訂(平成10年)によって、鑑賞指導を従来と同じように表現との関連を図って行うことを原則としつつも、全学年で発達や地域の実態に応じて独立した指導ができるようになった。また、美術館との連携を図ることが示されたことでより積極的で多面的な意義を鑑賞教育に認めようとしている。
これまでの鑑賞は、創造的自己表現を主眼とした教育課程の陰に隠れて、従属的な位置づけにあったといっても過言ではないだろう。確かに、子ども達の発達の道筋に合わせ、低学年での、自己を中心とした表現活動の中で自分や友達の絵のよさを認めたりすることを出発点として、発展的に芸術作品へ向かうという鑑賞が考慮されていたが、あくまで表現活動につなげることが前提であった。「子どもの視点」に立とうとするあまり、造形学習においては「自己表現」に価値が置かれ、「見る」ことや知覚重視の学習は忌避されてきたきらいがある。そこには、言語を主体とした美術作品の鑑賞活動(批判的分析など)は知識学習につながるという狭隘な見方があっただろうし、かつての学習指導要領にみられた「造形作品のよさや美しさなどを感じ取り」という表現は、鑑賞の質的側面が情緒的で感性的なものだという短絡的な認識を示していたと言える。学習指導要領におけるここ十年余りの変化は、ようやく「もしも作品と対話したいのならば、ことばでなくとも、コミュニケーションの方法を学ぶ必要があるはずだ。私達はそれを、どこで学べばよいのだろうか」(赤木里香子、「作品との出会い」美との対話8、山陽新聞、8/9、1994)という問題認識に応えようとしている証である。しかし、一方で鑑賞学習を「はじめにイメージありき」で芸術作品、それも純粋芸術から出発してその知覚的側面だけを強調することには注意を払っておく必要がある。
■鑑賞教育への関心の高まりの背景と現況
こうした美術教育における鑑賞への関心の背景をまとめてみたい。
(1)鑑賞メディアの変化
70年代以降のニュー・アート・ヒストリーの動向を受けて、美術史を「社会史」と見る考え方がなされるようになった。特徴としては、従来からの様式の分析、図像の解読、モノグラフの記述にとどまらず、顧客やパトロンとの関係、美術商やコレクターとの関連、画家とその家族、日常のあらゆる事実の収集と記述を行う。また、芸術(家)と社会的文脈との相互作用に視点を向けるものである。こうした流れの影響によってデジタルメディア、美術全集などが鑑賞を単なる様式区分や、色や形態の造形的要素だけに還元することなく、読みとりの方法論に対する示唆を与えるものに変化してきたのである。また、芸術作品の解釈や評価を言葉のみで概説するのではなく、多様な視覚資料を提示しながら、実証的な方法によって解釈を与えることで読者に絵解きの快楽を共有させるものになっている。また、子ども向けの芸術作品鑑賞関連書籍も増加しているが、その特徴としては、子どもに身近なテーマに沿った作品を提示したり、仕掛け絵本のように操作を必要とする部分を取り入れて興味関心を高めるようにしたものが多いことである。例えば、顔や動物といった作品の主題ごとに作品を提示したもの、作品をシールにして説明と合う箇所に貼るようになったもの、ジオラマのように組み立ての可能なもの、作品をヒントに自分で作品制作が可能な材料を添付したものなどがある。
また、電子メディアの発達によりCD-ROMやインターネット上で芸術作品・美術館情報が提供される。その利用上の特徴は以下のようにまとめられる。1)特定の概念に関連する代表的な美術を検索・提示する、2)各時代の美術様式、主題などの比較、対比を行なう、3)参考作品に情報を付加して提示をする、4)制作上の個別的な問題に見合う学習者のアイデアを補完したり、発展させる(メディアの扱い、主題の解釈など)、5)美学的概念に関して通時的に比較、対比する、6)美術作品を記述する概念や専門用語などを広範囲に検索する。
これらの変化は、鑑賞の契機を必ずしも作品自体に求めるのではなく、作品を取り巻く様々な状況をも含みもつことによって、美術教育における鑑賞を従来陥りがちであった表現技法上の参考資料的な扱いをする従属的な位置づけから、「見る」ことを主眼とした学習へと変容させる契機となった。また、図画工作科、美術科だけでなく、「総合的な学習の時間」においても芸術作品の扱いを多面的に位置づけることを可能にしたのである。
(2) 美術館教育の発展
欧米の美術館教育に触発されて日本でも美術館教育が1990年代に急速に発展し、各地の美術館においてワークシート、セルフガイド、ワークショップなどの開発が進み、来館者と所蔵作品を接近させる教育普及活動が活発化した。その間、「美術館教育研究」や『DOME』といった美術館教育関連の雑誌も出版されて美術館教育への関心の高まりを裏付けている。この動きと呼応するように、『大学美術教育学会誌』(大学美術教育学会)や『美術教育学』(美術科教育学会)に掲載された論文を見ると、美術館教育、鑑賞教育関連のものが、92年頃から急に増え始め、全体の約1割を占めるようになっている。題目の例としては、「ニューヨーク近代美術館における教育活動の理念、実践方法及びその歴史」「今日のアメリカの美術館教育−理論確立への動き」「美術館教育における『鑑賞』と『表現』の意義と可能性」などをあげることができる。
美術館における教育普及活動で開発された様々なアプローチは鑑賞学習の具体的な学習支援の方法と同時に楽しさを提供するエデュテインメント的要素の示唆につながった。鑑賞学習が表現学習に劣らず魅力的で子ども達の視覚的リテラシーの育成に寄与するものであるという認識を定着させてきたのである。
(4)アメリカの美術教育のDBAE(Discipline Based Art Education=学問に依拠した美術教育)の間接的影響
アメリカの戦後の美術教育において創造主義一辺倒であった状況への反省と教育カリキュラムにおける教科性の主張という教育行政的な戦略として60ユ年代頃からアカデミックな側面を前面に出した動きが見られるようになった。それが、学問の構造化の延長にあるDBAEである。その基底にある考え方は、創造表現のみならず、美術史、批評、美学などのアカデミックな領域からのアプローチを含めることで美術の知的な側面を強調し、教科としての明確な位置づけをねらったのである。特に教育的美術批評を提唱し、記述、分析、解釈、評価という一連の鑑賞手続きを提示したフェルドマン、批評的領域(経験的、造形的、象徴的、主題的、材料的、社会的)を重視しようとしたアイスナーらは、その先導的役割を担った。その考え方は、DBAEを標榜するゲティー財団の美術教育者や美術館教育スタッフが編纂したDBAEカリキュラム編成ガイド『学問に依拠した美術教育:カリキュラム・サンプラー』はもちろんのこと、『アドベンチャー・イン・アート』などのアメリカの商業的美術教科書全てに浸透している。
このDBAEの動向も間接的ながら日本の鑑賞学習のあり方に影響を与えた。アメリカの美術教科書自体はいずれも、造形概念の理解を主眼として芸術作品をその例証として扱うのが基本になっており、そのマニュアル化された構成は日本の美術教育にはなじまない。しかし、DBAEの考え方は、表現に対する子どものこだわりを背景で支える他者や芸術作品への批評的眼差しの育成がこれまで等閑視されてきたことの反省を促すには十分であった。
こうした背景によって美術教育における鑑賞の見直しがなされ、授業単位だけでなく、美術館と学校を結ぶ鑑賞学習の模索が進められようとしている。次にその具体例を示しながら問題点を探っていきたい。
■学校と美術館の連携の現状と問題点
ゲティー・センターのカリキュラムサンプラーには、「美術館、ギャラリー、地域の素材をどう利用していくのか?」という課題項目に対応してミドルスクールを対象とした「美術館において芸術の本物に触れる」題材案が示されている。このような美術館と学校をつなぐ鑑賞学習の試みは我が国でも様々な形で展開されようとしている。
€学校側で美術館教育の視点を取り入れた実践を行うもの
直接的に美術館との連携が図られるものではないが、美術館が提供するワークシートやワークショップの手法に倣って、学校の授業の中で自己完結的に鑑賞教育を行うものである。「エントランス美術館で遊ぼう」(大阪市日吉小学校)では、大阪市教育委員会の貸し出す実物大の複製画を利用して美術館教育で見られるワークシートの形式を取り入れて玄関に展示した作品鑑賞を行い、校内放送を通じて生徒の意見交換を行っている。
課外活動の選択肢の一つとして美術館訪問を位置づけて連携を図るもの
図画工作科や美術科の授業としてだけでなく、課外活動・行事・校外学習や総合的な学習の一環として美術館訪問を行い、そこで美術館の提供するギャラリートークやワークシートなどの教育普及活動に参加するものである。
東京国立近代美術館による「小・中学生のための鑑賞教室」、川崎市岡本太郎美術館のワークショップ、滋賀県立近代美術館のアートゲームなど学校と美術館の接近が最近では活発化している。1998年の川村記念美術館における「なぜこれがアートなの?」展では、豊田市美術館、水戸芸術館、アメリア・アレナス女史の共同企画によりギャラリートークを主体とした鑑賞教育の設定を行い、学校に参加を呼びかけた。学校でのスライドによる準備学習、美術館での本物との出会い、フィードバックというアメリア方式によって作品の見方についての意見交換が行われた。
また、兵庫県立近代美術館が2000年に開催した教育普及を目的とした「夏休み美術館 線を探しに」展では、タイトルが示すように夏期休暇中に子ども達を対象に学校単位の美術館訪問を呼びかけている。これを受けて、兵庫県花谷小学校では、学校における準備段階で抽象作家の展示作品の部分提示から全体の作品を予想させることによって子ども達の想像力を触発した後に、「ゲージュツに挑戦しよう」という投げかけで個別の表現活動に連動させた実践が行われた。最終的に美術館に作品を全員持参して元になった作家の作品と児童作品を比較した鑑賞授業展開が見られた。
¡学校と美術館とのコラボレーションによるより一体的な試みをするもの
最近では、学校の教師と美術館の学芸員がプロジェクトを組んで企画段階から連携を行うところも見られるようになってきた。岡山県立美術館では、2000年に「みることの再発見―もっと美術を楽しむために―」など新しい鑑賞方法を提案する展覧会を企画する一方で、県内の公立小中学校の教師との共同でギャラリーガイドによる教育普及活動の模索を行うなど、美術館の側もこれまで以上に積極的に学校との連携を図ろうとし始めている。
しかし、こうした美術館サイドの努力だけでは鑑賞学習の成果を上げることはできない。学校における美術教育が授業時間数削減のあおりを受け、鑑賞教育の重要性が示唆されながらも表現学習主体の授業という現実を変えるのは難しそうである。美術館が身近に存在する地域では今後ますます学校と美術館とのコラボレーションをすすめ協力関係を構築する必要があるのである。しかし、こうした連携が重視されようとしているものの、その距離はまだまだ縮まりそうにない。両者の連携を考える際に問題となる点を検討してみたい。
■子どもにとって鑑賞の成立するところ
子ども達、特に小学校低学年にとっての鑑賞は、芸術作品から出発するものではなく、生活や遊びを通して子ども達の感覚による発見、いわゆる「気づき」を重視し、イメージ化したり、ストーリーを膨らませる経験を充分積み重ねることが出発点になる。身の回りにある材料の「写し取り」(フロッタージュ)の活動を例に取れば、樹の幹や壁などを「写し取る行為」⇒「テクスチャーの違いの発見」⇒「見つける楽しさ」⇒「写し取り」という循環的なサイクルが生み出される。そこにも「見ること」(鑑賞)は成立するが、さらに学級全体でフロッタージュ作品からなる絵地図作りをしたり、どこで見つけたかをクイズにしたグループ活動を通して相互鑑賞の機会を設定したりして、見ることの共有化を図ることでさらに効果は増幅される。この場合のように、身体的感覚的な鑑賞の入り口を美術館自体では必ずしも保証できない。
宇都宮美術館の「森にいます」を始め、各地の美術館で見られるワークショップの多くが、鑑賞対象を所蔵作品に限定せず、作家を招待したりなどして体験的で感覚的なアプローチを館内外でする試み(主に表現活動)を行っているが、そのこと自体が鑑賞の対象や鑑賞の成立する場としての問題点を示している。作家を招待することなどは、学校での「総合的な学習の時間」の試みが進展するにつれ、地域の専門家を活用する事例も多く見られるようになり、美術館という場の必然性をもち得ないのである。
■本物の作品は切り札になり得るか?
美術館では、本物の芸術作品がそれなりのインパクトをもって迫ってくる。これ程までメディアが発達した時代にあって、「本物との出会い」という切り札に「作品の見方、親しみ方を知る」要素を加えて美術館は様々な教育普及活動を展開している。しかし、子ども達にとって、芸術作品が本物であることはどれだけの意味を持つのだろう。映画「トーマス・クラウン・アフェアー」(METRO GOLDWN MAYER PICTURES,1999)では、メトロポリタン美術館を暗示してはいるが架空の美術館の館内で引率教師が退屈気味の子ども達の興味を引き出すために作品(メトロポリタン美術館にあるはずもないモネの『印象』)のとほうもない「値段」を告げ、ようやく子ども達が驚愕の声をあげて作品に眼を見張る場面がある。ここに揶揄されるように、子どもにとって作品が本物であることは、必ずしも魅力のある存在を意味しない。それに彫刻作品に触れることができないなど、本物であることと引き換えに美術館にはタブーも多いのである。
徳島県にある企業が設立した大塚国際美術館には、「美術館」でありながら本物は存在しない。原寸大ではあるが陶板印刷によるいわゆるにせもの美術館であり、環境展示にしても作り物である点でそれこそバーチャル美術館なのである。しかし、果たしてこの美術館の存在を無視できるのであろうか。子どもにとっての鑑賞という点で言えば、スクロヴェーニ礼拝堂の壁面に描かれた宗教絵画は、大塚国際美術館で再現されていないならば、美術全集に一部が載せられているのがせいぜいであり、そのような古くささをもつ宗教絵画を子ども達は好んで見ようとはしないだろう。しかし、そのバーチャルな空間で、壁面に刻まれた15世紀や17世紀の恋人達の落書きを見いだす時、彼らの心はときめき、時代に想いを馳せるのである。そういった些細な部分が「見る」ことの動機をはらんでいることを無視することはできない。
2000年に大阪市立美術館では、「フェルメールとその時代」を開催したが、大阪教育大学附属天王寺小、中学校を始め大阪市内の多くの公立学校でフェルメールと関連した鑑賞授業がなされ子ども達が関心を示してそれなりの成果をあげた。それは毎日新聞社が主催していたこともあり、メディアを通じてある種のブランドイメージが形成されることで子どもだけでなく、父兄をも巻き込んだ美術館訪問へつながったことが要因である。つまりメディアが作り上げた「客寄せパンダ」効果によるものであった。子どもの身近な美術館に所蔵されていない作品は、結局目玉商品を冠した企画展や美術全集やインターネット上の美術館サイトでしかお目にかかれないし、CGやインスタレーションなど浮遊する作品群はなおさらである。美術館には、本物に触れること以上に鑑賞学習の方法論を提供することが期待されている。
■真の相補的な関係をめざして
学校は、「総合的な学習の時間」に示されるように、教育内容を直接学ぶのではなく、子ども達が主体的なテーマを設定して学び方を学ぶ教育の在り方へとシフトしつつある。美術教育も「感じ方」「見方」「表し方」「比べ方」といった方法概念を前面へ押し出した「方」の学習をひとり一人にどう保証していくのかという課題に応える必要性に迫られている。子どもにとっての「見る」学習は、作品のイメージからスタートするのではないこと、また、たとえスライドなどによる作品の提示でレンズの焦点がぼけていても「見る欲求」は誘発され、そこに既に鑑賞は始まっている。このような事態への認識をはじめとして、授業者には、「鑑賞」の概念的な捉え方から脱皮することが求められている。また、美術館との連携の際には鑑賞学習は美術館まかせにすればよいという無責任な意識を排除する主体性も必要である。
一方で、美術館には、単なる専門的知識の供与者として社会教育的な文脈での適合を目指すのではなく、鑑賞学習を展開する上での主体者として学校との相補的な関係を築くことが求められるだろう。