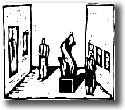
国立民族学博物館 吉田憲司
一方のルーヴル美術館は、フランス革命によるブルボン王朝の崩壊をうけて王室所蔵の絵画や彫刻、さらには亡命貴族や教会の財産を集め、1793年、国民公会の手で中央芸術博物館として開館した。ルーヴルの場合も、その初期には、ナポレオン三世によるメキシコ遠征時の収集品を受け入れたのをはじめ、数千点の「民族誌資料」を収蔵していた。しかし、それらの資料は、1828年以来ルーヴル内に設けられていた海事博物館に、1850年以降別置されるようになる。最終的にその資料は、1878年に設立されるトロカデロ民族誌博物館にうけつがれることになるが、ルーヴルは、一貫して美術館への特化の道を歩んだのである。
このルーヴルについて特筆すべきは、開館直後から、国ごと、流派ごとの展示区分が採用されたことである。絵を分類して並べるならば、絵の大きさ別に並べることも、また主題別に配列することもできたはずである。実際、ヴァティカンのピオ=クレメンテ美術館など、成立の古い小規模な美術館では、主題別の展示を選択した例もある。また、前代の「珍品陳列室」において、彫刻などについて素材別の分類が施されていたことはすでにみたとおりである。しかし、先に少しふれたように、18世紀になると、「巨匠」たちの評価の定着に合わせて、個人の美術陳列室においても、作家別・時代別の展示が採用されるようになる。美術を作家ごとの時系列の展開として語ることは、すでにルネサンス期のジョルジョ・ヴァザーリの著作『建築家・画家・彫刻家列伝』に端を発しているが、その語りを初の公共美術館としてのルーヴルが展示のなかで具体化することによって、それが以後の美術館における美術作品の分類・配列の基本原理となっていく。
ルーヴルにおける、この新しい流派別の展示構成の採用にあたっては、激しい議論があったという。当初、博物館の運営にかかわる委貝会のメンバーたちは「共和国における芸術と科学のあらゆる分野のあらゆる富を一堂のもとに集める」ことをなによりも優先し、総覧的な博物館を構想していた。そのなかで、国民公会の議員でもあった画家のジャック=ルイ・ダヴィッドは、そのような総覧的な展示はかつての「珍品陳列室」の延長でしかなく、「公衆の教育と共和国を代表する芸術家の育成」のためには、国どうし、作家どうしの比較が重要であるとし、それにはコレクションは流派ごとに分割し、時代順に配列されなければならないと、強く主張した。最終的に、このダヴィッドの主張が受け入れられたのであるが、新たに国家と国民を形成していくという時代の要請からすれば、それは当然の帰結であったといえるかもしれない。
時間軸に沿つて展示室が配置された美術館のなかでは、部屋から部屋へと巡り歩くことが、そのまま「美術」の歴史をたどることを意味する。ルーヴルを模して、その後欧米の各地に建てられた国家規模の美術館―たとえば、マドリッドのプラド美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館、ロンドンのナショナル・ギャラリTなどーーでも、それぞれの国や時代を代表する作家の作品を集めることで、同様の歴史の物語が再現されていった。そこでは、個々の「美術作品」は偉大な芸術上の「天才」の産物とされると同時に、美術史上の特定の国の特定の時代を代表するものとしてうけとられるようになる。美術館における現在のわれわれの経験のありかたの原型が、ここに誕生したといってよい。
現在のわれわれの経験のありかたという点でいえば、手を触れることなく展示物を見るという習慣もまた、この時代に成立している。開館当初の大英博物館の展示場が、すでにガラスケースを多用したものだったことは、1782年に博物館を訪れた、あるドイツ人の次のような述懐から明らかである。「残念ながら、私がみたのは、博物館そのものでなく、博物館の部屋、ガラス・ケース、それに収納棚だけだった。ひとつの展示部門から次の展示部門へと追い立てられるように足早に連れまわされたためである」。公共博物館とはいえ、開館当初の大英博物館は、一日の入場者も60人程度に制限され、案内係の職員についてまわるかたちでしか見学が許されなかったという。
ルーヴルにおいても、観客が自由に作品に近寄れない仕掛けが、開館当初から講じられていた。1805、6年ごろのグランド・ギャラリーの様子を描いたユベール・ロベールの絵が残されているが、壁際に柵が設けられ、絵を至近距離で見ることはかなわなかったことがうかがえる。「展示物に手をふれないでください」という、博物館・美術館でおきまりの制度、五感のなかで視覚だけを特権化するという志向は、博物館・美術館の成立とともに誕生していたのである。(おわり)
国立民族学博物館助教授。総合研究大学院大学助教授(併任)。文化人額学・博物館人類学専攻。1955年京都市生まれ。京都大学文学部卒業、大阪大学大学院博士課程修了。学術博士(1989年)。大阪大学文学部助手、国立民族学博物館助手を経て、1993年より現職。
1978年以来、主としてアフリカ、ヨーロッパ、日本でフィールドワークに従事。1990年から91年まで、大英博物館民族誌部門(人類博物館)客員研究員。主な著書に『赤道アフリカの仮面』(共著、国立民族学博物館)、『文化の「発見」』(岩波書店)、『異文化へのまなざし』(共編、NHKサービスセンタ-)などがある。