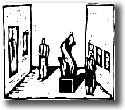
ミュージアムの成立(その2)
国立民族学博物館 吉田憲司
アンブラス城の「美術=驚異陳列室」
16世紀には、アルプスの北でも大規模なコレクションが成立してくる。なかでも、その規模の大きさで当時から名を知られていたのが、ハプスブルク家出身のチロルの大公、フェルディナント二世のコレクションである。インスブルック近郊のアンブラス城に設けたそのコレクションの陳列室を、大公みずからが「美術=驚異陳列室(Kunst und Wunderkammer)」と呼んでいるが、その名のとおりコレクションの内容はきわめて雑多であった。壁には床から天井まで絵画がかけられ、天井からは剥製のワニやサメがぶら下げられていた。一方、部屋のなかには多くの収納キャビネットが並べられ、そのなかにさまざまな器物が主として素材別に分類されて収められた。岩石の標本や珊瑚、魚の化石、「巨人」の骨(じつは恐竜の化石)などの自然界の産物が並んでいるかと思えば、自動機械や時計、磁石などの科学機器、古銭、異国の産物が、ユダが自ら首を吊って果てた際に用いたロープの切れ端や、ソロモンの神殿で使われていた木釘(ともに今は失われて所在は不明である)といったあやしげな品物とともにつめこまれていた。「異国の産物」のなかには、西アフリカのベニン王国でポルトガル人の注文に応じて作られた、いわゆるアフロ=ポルトギーズの象牙製スプーンや、コルテスが「新世界」からもたらしたプレ=コロンビア期の羽根製の頭飾りも含まれている。フェルディナント二世は、その頭飾りの羽根を抜いて自らの婚礼の際の頭飾りに用いたという。当時、こうした「異国の産物」の詳細な製作地については、ほとんど注意が払われなかった。たとえば、右で触れたベニン王国の象牙製スプーンについても、フェルディナント二世の死後一五九六年にまとめられた資財帳には、「トルコ風のモチTフをもつ非常に細いスプーン」という記載がなされているのみである。
このように、自然界の産物と人間の産物、古代の遺物と異国の器物を一堂に集めることで、当時の「珍品陳列室」は、そのまま世界の縮図、ミクロコスモスを実現していたといってよい。しかも、自然の産物と人間の産物、時間と空間を異にする多様な器物は、同じ素材ごとに分類されることでひとつの蓮鎖をなし、さらにはそれぞれの素材にみとめられた神秘的な力の点でもつながっていた。「珍品陳列室」は、神の創り出した存在の連鎖の証明の場でもあったのである。そこでは、コレクションは、その持ち主の世界に対する該博な知識を示すだけでなく、同時にその持ち主が世界を所有する力を誇るものともなった。コレクションを構成するひとつひとつのものは、そのものがもともと属していた文化について語るよりも、まずもって、それを集めた人物の力と地位を語るものとして用いられたのである。
学者のコレクションと王侯貴族のコレクション
17世紀も後半に近くなると、全体でひとつの世界を写し取つていたコレクションに変化がおこり始める。「巨匠」たちの手になる「美術作品」に高い価値を認める価値観の広がりに合わせて、コレクションにも、美術品のコレクションと自然の産物のコレクションとの分化が進み、王侯貴族は美術品を、一方の学者や医師は自然界の標本を集めるという流れがきわだってくる。
17世紀のデンマーク王室で、クリスティアン四世やフレデリク三世ら、王のコレクションのアドヴァイザー
を務めていた医学者オーレ・ウォルムの個人のコレクションの様子を示す版画が残されている。ウォルム自身が編纂した『ウォルムのミュージアム』の表紙を飾った版画である。ウォルムは、コベンハーゲンの大学で「自然哲学」の教鞭をとるかたわら、自然界の産物や異国の産品を大量に収集していた。彼の「ミュージアム」の内部には、多様な標本が所狭しと並べられ、初期の「驚異の部屋」の様子をよく伝えている。興味深いのは、収集された標本についての解説の多くに、薬としての処方が記載されていることである。彼は、当時の本草学の知識に基づき、薬としての使用を念頭において、こうした自然界の標本や珍品の収集にあたっていたのである。
ウォルムに限らず、本草学的なコレクションを築きあげた医師や学者が、王侯貢族の美術品コレクションのアドヴァイスをするというのは、当時のヨーロッパで広くみられる傾向であった。ドイツ・ミュンヘンのアルブレヒト五世、ヴィルヘルム五世による美術陳列室の収集に指針を与えたのは医師ザムエル・クヴィッヒェベルクであったし、イギリスにおいて、バッキンガム侯ジョージ・ヴィリエールの保護を受け、「トラデスキャントの方舟」としてしられる巨大なコレクションを築き上げたジョン・トラデスキャントもまた、本草学の専門家であった。このため、初期の美術陳列室の絵画・彫刻の陳列方法には、医師や学者による自然界の標本の陳列方法との並行性がみとめられることが多い。たとえば、18世紀初頭のマンハイム選帝侯の絵画のギャラリーの様子をみると、雑多な絵が寄せ集められ、その多様性と量で見る者を圧倒するという、「ウォルムのミュージアム」と同様のマニエリスム的感覚をそこにみてとることができる。(つづく)
国立民族学博物館助教授。総合研究大学院大学助教授(併任)。文化人額学・博物館人類学専攻。1955年京都市生まれ。京都大学文学部卒業、大阪大学大学院博士課程修了。学術博士(1989年)。大阪大学文学部助手、国立民族学博物館助手を経て、1993年より現職。
1978年以来、主としてアフリカ、ヨーロッパ、日本でフィールドワークに従事。1990年から91年まで、大英博物館民族誌部門(人類博物館)客員研究員。主な著書に『赤道アフリカの仮面』(共著、国立民族学博物館)、『文化の「発見」』(岩波書店)、『異文化へのまなざし』(共編、NHKサービスセンタ-)などがある。