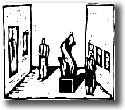
現代美術の受けとめ方
倉敷市立美術館学芸員 前田 興
少し前のことになるが、日本とアメリカの教育の違いについて日米両国で授業を受けた日本人高校生約千人のアンケ−ト調査結果が発表されていた。それによると、大学入試に合格するのを目標にした教え方では高校生の55%が日本を評価、アメリカの方が良いとする回答は1%にすぎなかったのに対し、独創性に富んだ思考を育てる教え方ではアメリカの教育を支持する回答は52%、日本は1%だったという。受験を目標にした教育の弊害はおそらく様々な形で表われてくるだろう。独創性を生命とする美術の分野の歪みも気になっていたところ、ニュ−ヨ−ク近代美術館で、現代美術の受けとめかたについて講義を受ける機会に恵まれた。いろいろ考えさせられる点も多かったので、少し紹介してみたい。
『なぜ、これがアートなの?』(淡交社)といった著書で日本でも有名になったアメリア・アレナス氏の講義は、いきなり中世のガラス製容器をスライドで見せて、「この作品のどこがいいの?」と問いかけることから始まった。「この作品がデパ−トの食器売り場に並んでいたら、みんな感動する?」と尋ねられる。私たちは「美術とは何だろう?」と改めて考える。次に京都・浄瑠璃寺の吉祥天立像のスライド。この作品について何も知らないニュ−ヨ−クの人はどう思うか。そうした人々の反応をアレナス氏は次の3通りに分析した。まず世間の常識で判断する人は、漠然と女性美を表わしたものであると受けとめる。次に自分の体験にひきよせて作品を見る人は、リンゴをあげるからそこに座りなさいと言っている母親の像であると言う。そして、象徴的なもの(たとえば宝珠)に意味づけして考える人は、東洋のマリア像ではないかと判断するかもしれない。もちろん3者とも不十分な見方ではあるが、なじみの薄い美術作品に対したとき、私たちもこれらの人々と五十歩百歩の受けとめかたをしているのではないだろうか。作品を正しく鑑賞するためには、自分の目で美を見出す感性と、表現の本質を見抜く知性の修練が必要である、というのが氏の意見だった。
では、私たちはどこにポイントを置いて修練を積んでいけばよいのだろうか。この点について、『モダンア−トの見かた』(美術出版社)という著書を出したフィリップ・ヤノワィン氏は、美術の鑑賞者を次の5段階に分けて説明した。まず第1段階の鑑賞者の特徴は、作品を見るのが早いことにある。つまり作品そのものを注意深く見ようとはせず、一瞥して自分なりに即断してしまう。たとえば台形の山が描かれていたら、すぐに富士山と決めつけてしまう。彼らは、まず作品をじっくりと見ることが大切である。次に第2段階の鑑賞者。彼らは自分の判断に疑問を持つ。さきほどの富士山の例でいうと「たぶん富士山ではないか」という言いかたになる。また作品のプレ−トを見て、たとえば、そこにピカソ作と書かれてあれば絵を見る。彼らは他人の評価に従って作品を見ている。こうした人々には自分の感受性に自信を持たせるような声援が必要である。第3段階の鑑賞者は知識先行型の人。よく学び、多くのことを知っている。反面、権威に追随するタイプの人も多い。しかし、知識の壁が災いして、新しい美を積極的に認めることができない。この段階の人はもっと独創性を重視すべきである。第4段階の鑑賞者とは常識や知識の枠を突き抜け、自分の感性と知性で作品をとらえることができる人々である。こうなれば、美術作品に対して意見を述べても説得力が生まれてくるだろう。最後に第5段階の鑑賞者。この段階は、基本的に美術イコ−ル人生といった覚悟がなければ到達することができない。美術の鑑賞を通して自分が生きていることを再確認し、人生最大の喜びとするには長い時間が必要である。これこそ美術を楽しむ究極の姿勢である、とヤノワィン氏は説く。
戦後の美術はますます多様化が進み、具象的な表現からすれば理解しにくい作品が増えてきた。従って、見る側にもそれに応じた対しかたが要求されるようになった。両氏の論でも分かるとおり、心地よい美しさという既成概念を超えて、見る人に強烈なショックを与える作品に果敢に対峙していくことが必要になってきているのが現状である。そればかりか、作者より提示されるものをおとなしく受けとるだけでなく、見る者が積極的に参加することの意義を意識することが必要になる時代になってきているのではないだろうか。現代の美術を考えるとき、作り手の側だけでなく、鑑賞する側にも深く考えが及んでいるニュ−ヨ−ク近代美術館の姿勢に驚きと共感を抱くとともに、独創性に富んだ思考をすることが苦手な日本人と21世紀の美術の間に不安を感じないわけにはいかなかった。
