
美術鑑賞と美術鑑賞教育は違う
奥本素子
美術鑑賞と美術鑑賞教育は違う。なぜなら美術鑑賞は意義や目標などがなくても成立するが、美術鑑賞教育は鑑賞というものを人に教える以上そこに確固たる意義がなければならないからだ。ではなぜ美術鑑賞は人々に広めなければならないのか。そしてどの様な美術鑑賞を人に伝えるべきなのだろう。多くの人が美術に触れなくても、何の支障もなく生きている。それなのに我々は義務教育のカリキュラムに美術鑑賞を組み込み、社会教育機関として美術館を税金で運営し続けている。美術に興味がない人にとって、それは時間と金の無駄である。だから現実には不況にあえぐ現在美術館の閉館が相次ぎ、学力低下に悩む教育界では美術鑑賞の授業数を減らしていく。しかし大義名分としてだけ美術館が存在し、美術鑑賞が国民の権利として保障されている。
自由に感性を使って美術を見せるという幻想が、このような一部の人だけの楽しみのために美術館や美術鑑賞教育が保障されているという状況を生み出したのである。美術館を保護し、美術鑑賞教育を唱える人は、概して美術鑑賞が好きで、それにいたく感動している人々である。しかしこの世に美術が好きな人もいれば音楽が好きな人もいて、歴史が好きな人がいて科学が好きな人がいるように、美術を好き嫌いで語るとそれは個人の資質に関わる問題になってくる。全員に真っ白な状態で美術を好きになれというのは無理であるし、美術作品を自己の感性を働かせ自由に見るべきだと教えても、美術に対して感性が働かない人もいるのである。
美術鑑賞を教育として捉えるのは、美術に触手が伸びない人にも美術の存在意義というものを知ってもらい、美術作品の保護や創造に理解を示してもらうためである。では美術の存在意義とは何であろう。皆が共通して享受できる意義とは、癒しや感動といった感性的なものではなく、美術作品を通じて語られている文化、思想といったメッセージの方である。文化や芸術を通じて人は教養を深めるという。広辞苑の定義によると、『教養とは単なる学殖・多識とは異なり、一定の文化理想を体得し、それによって個人が身につけた創造的な理解力や知識のこと』であるという。つまり自分なりの哲学や見方というものを獲得するためには、我々は一定の文化や理想を知り世界観を広げ、それを応用して創造的な自分の見方というものを生み出さなければならないのだ。そして美術作品や芸術作品と呼ばれるものは、文化や理想を我々に伝えてくれるメッセージであるのだ。だから文化芸術に造詣の深い人は、そこから多くのメッセージを受け取れ、より広い視野を身につけ、より深い思想を確立できているのである。教育では美術や芸術を知ることも人間形成にとって必要なことだと考えているし、教育で美術を取り上げる以上、ただ楽しいや面白いといった快楽だけではなく、何らかのことをそこから学んで欲しいと考えているのである。
事象の正しい解釈と理解力を高め、それを自らの現実に反映して問題解決に当たっていくこと、これは美術鑑賞といえども他教科の学習法となんら変わりはない。ただ美術鑑賞で扱う事象というものが曖昧で正解のないものであるということと、その先にある問題というものが試験問題ではなく芸術家が作品を通じて取り組んだ文化多様性であったり、美学であったり、戦争や平和であったりするだけなのだ。
では、正しい理解と、的確な応用性を身につけるためにはどうすればいいのだろうか。現在、学習科学や認知心理学と呼ばれる分野では、人の正しい理解や効果的な学習法を科学的に、もしくは心理学的に分析して、それを教育プログラムに応用している。美術鑑賞教育においても、その様な理論の応用が可能ではないだろうか。本論では美術鑑賞教育における認知心理学や学習科学の応用の妥当性、その理論の詳細、そして理論や分析に基づいた美術鑑賞教育のプログラムの提示などを行なっていく。
美術鑑賞教育に教育論の応用は可能である
美術鑑賞教育が、感性教育ではなく、作品の読解力と、そこから得たメッセージの現実世界の応用であると定義づけした時点で、美術鑑賞教育は他教科の学習となんら代わりはない、と言うことは主張できる。しかし依然として、美術鑑賞教育の扱う分野が美術作品という曖昧なものであるということや、その解釈に正解がないという点から、通常の学習と同様に考えることに抵抗があるかもしれない。では以下に美術鑑賞教育独自の問題だと考えられていたことが、実は多くの教科に当てはまる学習と教育の問題に共通しているということを証明していこう。
<美術鑑賞教育特有の問題>
1 教えること自体が抽象的
1.1 文化・芸術は概念のため、概念自体が抽象的で、教えることを確定するのが難しい
1.2 正しい美術鑑賞というものが確立していない
2 教える意義が曖昧
2.1 文化・芸術や美術鑑賞とは教えられて身につくものなのだろうか
2.2 美術鑑賞法を教えることで、人は本当に発展していけるのだろうか
3 教育論が曖昧
3.1 どの様に教えるべきなのか
3.2 どの様な効果があるのか、その測定法とは
以上の点が美術鑑賞教育を語ることを困難にし、それを教育的観点から論ずることに抵抗を与えている主な問題点である。しかしこれらの課題は何も美術鑑賞教育に限ったことではなく、教育全般が抱える問題点なのである。
まず教えること自体が抽象的だというが、数学でも理科でも社会でも、人間が生み出した学問というものは全て概念であり、あるのは定説のみである。それを真実として学習者に覚えさせる学習法と、その概念を学習者が理解する学習法がある。どの学問もどちらか一つの学習法を採用している。たとえば数学に関しても、掛け算のやり方を九九などで丸暗記する方法と、実際商売を行ないながら金銭授受の中でそれを学ぶやり方がある。文化・芸術のようにその概念が曖昧で教えることが困難だとするのならば、後者の学習者自身が文化や芸術に触れることでその概念を構成する学習法を採用すればいいのである。この学習法を構成主義と呼ぶ。そして現在、構成主義でも効果的な教授法があるのではないか、という研究が進んでいる。それが社会構成主義と呼ばれる考えから発展していった学習論であるが、後に詳しく語る。
さらに正しい美術鑑賞というものが確立していない、というが、熟練した美術鑑賞というものは存在する。例えば西洋画の熟達者はただ先人の絵をぼんやりと見ているわけではないという。「よく学生と一緒に絵を見るのに、こういう定規を使ってこういうことをしてみるんですよ、こういうことをしてみると、ああ、ちょうどこの黒は、ここの水平線のところで終わっているなとかね・・・必ずそういう風にだけやっているわけではないんだけど、非常に面白いものはあるんです。・・・文章読むのは大変だけど、絵を読むのは、だから学生に言うのも変だけど、絵もよまなきゃいけないんだよって言ってるんですよ。絵というものは、普通の文章と違って、普通の文章は読む順番というか、書いてることが皆決まっているけど、絵は自分の思い通りに呼んでいくわけ。だから絵の読み方の方が難しいけど、内容のある人が読めば、内容を余計読むんだと。」(大浦、pp.5-112)他の研究者の報告でも、熟達者の美術鑑賞は内容に対する深い洞察と妥当な分析によって成立しているという。さらにそれらの知識や観察を通して、彼らは自分なりの作品解釈というものに繋げているのである。絵画鑑賞の熟達者の特徴は、他分野の熟達者の特長にも一致する。チェス・歴史・科学・数学などの領域の熟達者は自分の専門分野に関する豊かな知識体系に基づき、優れた思考力や問題解決能力を発揮している。美術鑑賞教育でも目指すものとは、この熟達者のように美術作品に対する知識と自己判断能力の発展させることではないだろうか。
また、美術鑑賞は教えることで身につくのか、という問題であるが、教えることによって身につくかどうかは定かではないが、美術鑑賞というものはきっかけや慣習がないとなかなか定着しないというのは事実である。フランスの社会学者、ブルデューの調査によると、美術に対する造詣というものは家庭環境に左右されるという結果が出ている。これは日本で行った美術館来館者と学歴の相関図からも伺える。大衆文化と違って教養文化と呼ばれるハイクラスの文化は、その文化への造詣の深い大人がいて初めてそれが伝えられる。両親や家庭内の人が美術に興味がない環境では、子どもの美術に関する興味も育たない。イギリスの国立教育研究財団の調べでは、芸術活動に参加している若者の多くは芸術に親しむようになったきっかけは家族のメンバーによるものであった。しかしクラス4と5の若者に関しては、教師から強い影響を受けてきたという。(イギリスの階級社会は主に5〜6つのクラスに分けられる。クラス4と5は最下層のクラスの若者であり、親の職業は肉体労働者(職人を除く)や失業者である場合が多い。)つまり美術鑑賞とは教えられて身につくかどうかは別にして、美術を鑑賞する機会と環境を与えられない限り身につかないのである。さらに美術館での調査によると、子どもを美術館に連れてきている保護者のほとんどが何らかのアドバイスを子どもに与えているという。通常、家庭では美術鑑賞の機会を与えるとともに、その見方についても教えているようだ。美術鑑賞と教育は案外密接に関わっているのかもしれない、ということがこれらの調査で判断できる。
さらに的確な教授を行なえばその能力は発展するのか、という問題であるが、認知学者のアビゲイル・ハウゼンが考え出した美術鑑賞カリキュラムでは、彼女のカリキュラムを採用したクラスとそうでないクラスの生徒の鑑賞能力の違いがあるという報告を出している。
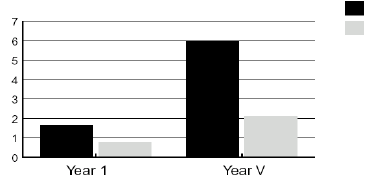
図1 文脈意味理解テストにおけるスコアの違い(一年後と五年後)
つまり美術鑑賞であっても、教育目標とそのカリキュラムを教育科学的に組み立てれば、それなりの成果が上がるということである。ハウゼンのカリキュラムやその目指すところが妥当かどうかという疑問はさておき、美術鑑賞でも教育学的に分析、発展させていくことは可能なのである。
そして美術を鑑賞する能力を身につけることによって、人間の能力はどの様に発展できるのかについての研究は、アメリカで古くから着目されている研究である。美術作品という抽象的なメッセージを観察と知識によって読み解く能力を発展させることによって、数学の抽象概念が理解できたり、国語の読解能力が上がったりするという結果が生まれている。また観察眼を養うことが、問題を読み解くことへの注意力や集中力を育むという結果もある。教科学習だけでなく、文化を知り、芸術を知ることは、自分の文化への愛着や多文化への理解を促進し、社会教育にも繋がっていくのである。
以上のように、美術鑑賞を教育に組み込む意義というものは存在する。ただし、その教育論が確立されていないのは事実である。私は美術鑑賞教育を他教科と分けて考える必要はないと思う。美術鑑賞であっても知識というものがなくては熟達した鑑賞者にはなれないし、他教科であっても知識の応用力や創造力といったものがなければ学習の意義がないと現在考えられている。そして最新の学習論で情報の正しい解釈と共に、創造性を発展させることや、学習者自身の意欲を刺激することも、重要な教育の一部であるという解釈がなされて、それに対する研究が進んでいる。その様な最新の学習研究を応用すれば美術鑑賞教育も効果的で的確な学習法というものを確立することが出来るのではないか。
現在の認知心理学の掲げる学習論は、従来の暗記中心や教授中心型の学習法ではなく、生徒が自発的に学び、それを教師や大人や環境がサポートするという形式が取られている。さらに知識それ自体への関心だけでなく、そこからの応用力や創造性の発展というものも組み込んだ学習支援になっている。そのため、美術鑑賞に必要な解釈能力や創造性を育む際にも、参考に出来る部分が多々あるのだ。

2003年8月 同志社大学文学部美学および芸術学専攻 卒業
2005年7月 Northumbria University MA Museum and Heritage Management 卒業
所属学会
美術科教育学会 日本ミュージアムマネージメント学会