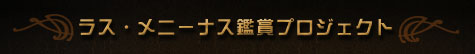鑑賞教育に熱い視線が注がれていますが、これまで鑑賞教育は、創造的自己表現活動の陰に隠れて、従属的な位置づけにあったといっても過言ではありません。せいぜい授業の終末時に自他の作品の「よさ」を認める相互鑑賞活動や、表現技法上の参考として芸術作品へ向かうことはあっても、「見る」ことを真正面から受け止めた実践事例は少なかったのが実情です。その背景には、言語を主体とした鑑賞は知識学習につながるという狭隘な見方があったでしょうし、鑑賞の質的側面が情緒的で感覚的なものにとどまるという短絡的な認識を示していたと言えるのではないでしょうか。しかしこうした鑑賞教育のあり方についての議論がようやく活発化していると思われます。
学校における鑑賞教育といえば名画鑑賞といったイメージに陥りやすく、作家の表現意図や心情の感じ取りを中心にした鑑賞教育が方法論の中心として捉えられがちでした。最近の鑑賞教育研究を見ると、作品や作家についての知識や固定化された見方を教え込む従来型の知識偏重の鑑賞教育からの脱却の可能性を探るものが多くなっています。その中で美術館の教育普及活動に由来するビジュアル・シンキング・ストラテジーや対話型鑑賞と呼ばれる方法が注目を集めていますが、同時にそれに対する批判も見受けられます。
鑑賞の対象を芸術作品だけでなくより広く捉えるべきではないのか、名画の場合には知識・情報をどの程度把握しておけばよいのか、子どもの解釈をどう受け止め評価していくのかなど、鑑賞に対する課題は多くあります。
今回、敢えて名画と言われるベラスケスの「ラス・メニーナス」(宮廷の侍女たち)を共通の鑑賞対象として、全国の小学校、中学校の先生方にそれぞれの考える鑑賞教育実践を呼びかけ、ラス・メニーナス鑑賞プロジェクトとして鑑賞学習の可能性と課題について話し合ってきました。その実践の概略については、「ベラスケスの『ラス・メニーナス』鑑賞学習をデザインする」(2006・10月発行・問い合わせ先:日本文教出版社)という冊子の方に載せ、このサイトにはその詳細を紹介するという連携形態をとっております。このホームページと冊子とを活用していただき、鑑賞学習の論議を深める糸口になれば幸いです。
ラス・メニーナス鑑賞プロジェクト代表者 兵庫教育大学連合大学院研究主幹 福 本 謹 一
問い合わせ:fukumo@hyogo-u.ac.jp