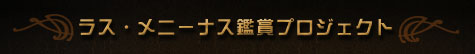 |
|
検討事項 |
|
ラス・メニーナス鑑賞プロジェクトでは、小学校、中学校それぞれ4人の先生方が実践を行い、2回にわたって検討会をもった。 鑑賞対象としてのラス・メニーナス プロジェクトを開始した際に先生方が問題としたのは、鑑賞対象としての「ラス・メニーナス」の適切性である。西洋美術史の中のバロック期の名画ではあっても、子どもたちにとっては、全体が暗い表現であることや主題の難しさ、子どもにとっての必然性などが指摘され、授業導入に対する不安感が漏らされた。しかし、実践を行うことで子どもたちが、人物が多く描かれていることで親和性を持ったことや様々な謎解きに出会うことで、作品を「見る」ことの楽しさを増幅させたことが指摘された。 プロジェクト自体は、ラス・メニーナスの鑑賞を前提としていたが、ラス・メニーナス一作品に限定するものではなく、関連作品を取り上げるなど取り組み方は自由であった。ピカソの作品が参考として取り上げられた例はあったが、あくまでベラスケス作品に焦点化された。今後、配当時間を広げることや鑑賞の積み重ねができれば、福田美蘭やウィトキン(写真)などのオマージュ作品、引用作品を取り上げて比較鑑賞するなどの構想も可能になるだろう。 授業の内容と方法 鑑賞授業の内容としては、ラス・メニーナスに関する情報の扱いによって実践が異なっている。ベラスケスやラス・メニーナスの書誌的情報など基礎的な情報を与えてから子どもの活動に移行する場合や背景知識などの情報を全く与えずに、作品という視覚情報だけに直接向き合わさせる場合など様々であった。 定着させるべき一定の知識を重要視する場合には、ある程度背景となる美術史や社会史の知識を前提として鑑賞学習が成立すると考えられる。逆に子ども自身の見方や気づきを優先させようとする場合には、むしろそうした知識が「見る」ことを阻害する場合もあるだろう。 方法的にはある種の流行とも言える対話型の鑑賞を中心にしたものが多かったが、美術館のギャラリートークのように決して作品だけを相手として行うのではなく、人物カードのような具体的操作を導入してモチーフに焦点化することや、話し合いの中で子どもたちの発話のキーワードを板書して観点を整理して自他の意見を相対化しやすいようにしたり、あるいはワークシートを活用して記述によって自分の意見をより客観的かつ論理的にまとめることを期待するなど、いわゆる教具の活用がなされ、対話を単なる交流活動としてとらえるのではなく、振り返りを含めて学習として成立させていることである。当然ではあるが、教室における鑑賞は、鑑賞対象自体は複製を利用せざるを得ないが、美術館における鑑賞とは異なったアプローチが目指されるべきである、 特に小学校の場合には実践にも見られるように、具体的操作を組み込んだ体感型の鑑賞が表現との関連の中で目指されていることは先生方の授業設計における必然的な帰結であろう。光や鏡、空間配置の問題を「謎」や「不思議」として設定し、子どもたちの興味・関心につなげながら「物語」や想像の形で作品世界と自分との関係性をしっかりと築き上げることをねらいとしているのである。 対話型鑑賞と他教科との関連 対話型鑑賞は、図工科や美術科に特化した方法ではなく、国語科や社会科でも行われるものである。コミュニケーション能力を育成することは、通教科的に望まれていることであるが、鑑賞対象を前にして対話型の学習を行うことは他教科でも行われる。社会科でも視覚資料を元に「昔の暮らしを見つけよう」といった形で同様の活動は行われるが、あくまで学習の目標は社会的な事実を分析したり、時代背景を読み取ることであり、その資料となった画像自体の作者の心情や造形的な分析、あるいは感じ方自体を問題にすることを行うわけではない。鑑賞教育における対話型鑑賞は、子どもの気づき・発見に基づきながら対象となるものの造形的な特質まで踏み込んで他者との意見の相対化によって自分の考え方の位置づけを明確にしたり、自他の意見を尊重したりすることが望ましいだろう。 表現と鑑賞の一体化 図工科における鑑賞学習では、何らかの表現活動との連携や一体化という形で実践されている。絵巻物、お話作り、物語をベースにしたジオラマ制作、鏡を使った空間構成といったように表現活動が展開されている。「私のラス・メニーナス」という題名にも見られるように、子どもたちにとってのラス・メニーナス鑑賞は、通説といったようなある種の答えに収斂する方向ではなく、意見交流も含めて、表現活動に置き換える中で、独自の見方、表し方、考え方といった個別的で機能的な学力を提示することが期待されているのである。このことは対象自体の価値を軽視するものではなく、子どもたちのそれぞれの向かい方を広げ、表現された内容に子どもなりに鋭く迫ることにつながることを直感的に認識しているからに他ならないだろう。 評価の課題 美術科の場合には特に評価の問題が重要視される。鑑賞授業をどう評価につなげるのかは共通した課題であり、中学校の先生方は、授業と期末考査との問題の連携を図る工夫をされた。美術資料集に基づいた形式的な作問ではなく、対話型鑑賞で得た学習の成果を作問として生かして独自の問題開発(初出問題場面応用テスト)をされた場合もある。この提案は鑑賞領域の評価が困難とされることに対して一つの答えとなるにちがいない。 学習の成果 あるアンケート結果では、教師が鑑賞学習を実践することに自信がない理由に知識が限られていることがある。作品研究は重要であるが、知識伝達が目的化したり、知識自体に価値を置いたりすることよりも、子どもなりの感じ方や見方を主体的に身につけたり、多様な表現に気づいたりすることの方が重要である。実践にあたった先生方は、ラス・メニーナスを鑑賞題材として設定する中で教教材研究として作品解釈について情報を様々な資料から得ているが、それを柔軟に授業構想に結びつけている。ラス・メニーナス作品が鏡面像を描いたという立場をとることで鏡の利用による操作活動を展開することになったり、奥の鏡に映じた国王夫妻の位置に関門代意識を持つ場合にはジオラマ的な空間構成が構想につながっている。 こうした授業の成果として共通して指摘されたことは、「見る」という行為や対話を通して、表現活動をする際の主題設定の前提となる意図の重要さを感じとったことや、作品に潜む様々な見方の交流から鑑賞学習の追求につながる契機とすることが可能になったことである。 鑑賞学習は、「知識」といった言葉に惑わされず、まず肩の力を抜いて実践することが大切である。 鑑賞学習の拡がり 鑑賞学習が注目されてきたと言っても、授業としての実施率は表現学習に比較すればわずかにすぎないのが実状である。鑑賞学習の実践が積み重ねられていくことで鑑賞と表現との関わりについても論議を深めていくことが可能になる。多くの先生方に積み重ねを期待したい。 最後に、プロジェクトに参加していただき授業実践された先生方のみならず、プロジェクトの報告書として具体化する機会を与えてくださった日本文教出版の柴田謙二郎氏並びに河野芳隆氏に謝意を表したい、 (福本謹一) |
| 参考資料 書籍 大高保二郎著,『世界美術大全集 第16巻 バロックⅠ~ベラスケスとマドリード派~』,小学館,1994 谷川渥著,『鏡と皮膚-芸術のミュトロギア-』,ポーラ文化研究所,1994 西川和子著,『スペイン宮廷物語 王女マルガリータへの旅』,彩流社,1994 『ベラスケス』,週刊グレート・アーティスト(分冊百科・西洋絵画の巨匠たち),同朋舎,1990 ケネス・クラーク著,『絵画の見かた』,白水社,2003 アメリア・アレナス著,『人はなぜ傑作に夢中になるの』,淡光社,1999 アメリア・アレナス著,『みる かんがえる はなす』,淡光社,2001 上野行一監修,『まなざしの共有 アメリア・アレナスの鑑賞教育に学ぶ』,淡光社,2001 マイケル・J・パーソンズ著,『絵画の見方 美的経験の認知発達』,法政大学出版局,1996 木村重信・高階秀爾・樺山絃一監修,『絵の中の時間』,NHK日曜美術館 名画への旅,講談社,1994 ミッシェル・フーコー著,渡辺一民・佐々木明訳,『言葉と物』,新潮社,1974 佐々木正人著,『レイアウトの法則』,春秋社,2003 小林康夫著,『表象の光学』,未来社,2003 川崎寿彦著,『鏡のマニエリスム』,研究者出版,1978 福本謹一他編集,『美術フォーラム21』,第11号,2005 福本謹一・赤木里香子編著,『図画工作科鑑賞学習のアイデア46』,2003 ビデオ 『ベラスケス~素顔の宮廷画家~』「世界・美の旅」,テレビ東京(日経映像), |
